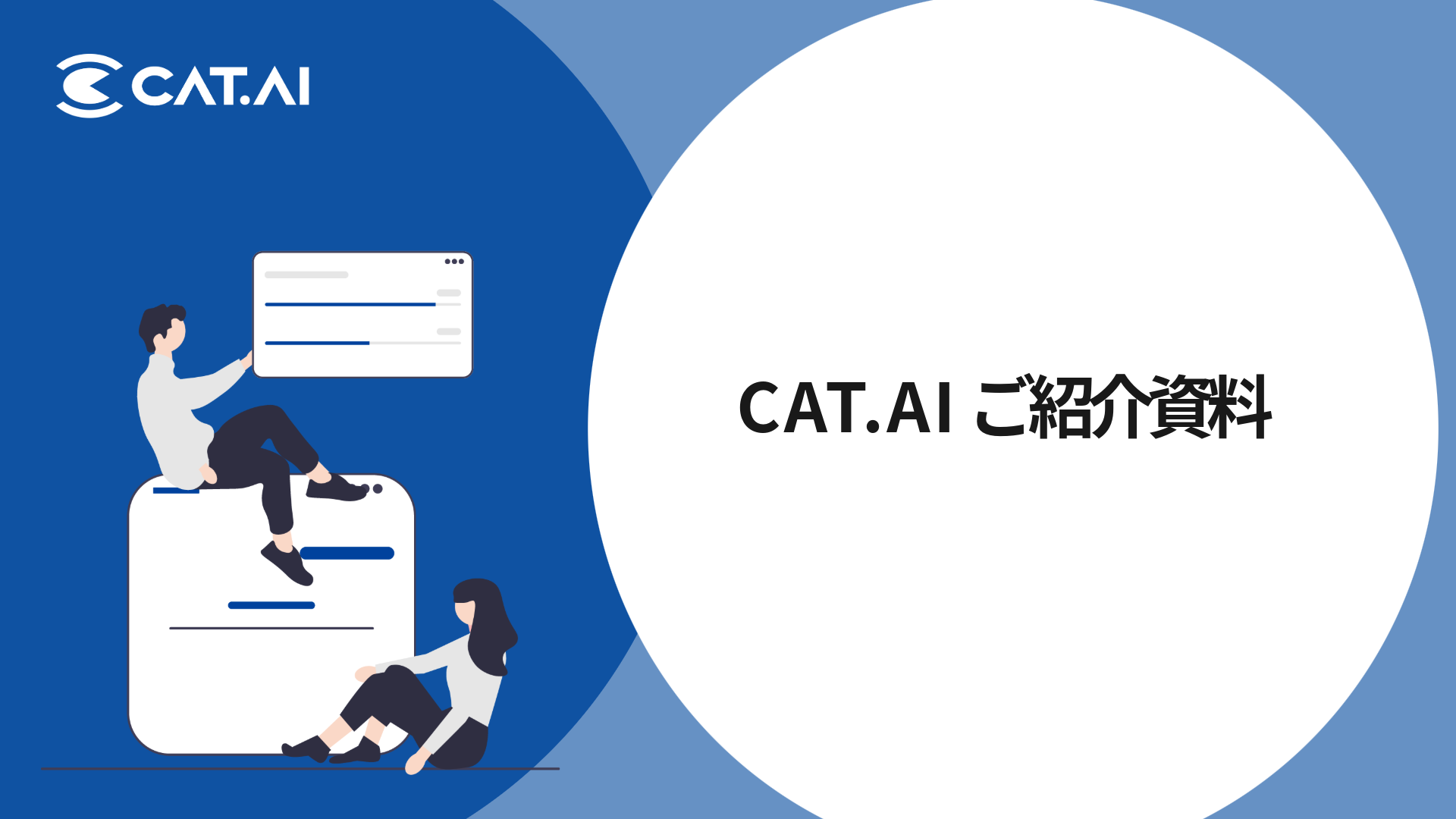自律型AIエージェントとは?基本的な考え方と活用のポイント

業務効率化やDX推進を目的に、生成AIやチャットボットの導入を検討する企業が増える中で、「自律型AIエージェント」という言葉を目にする機会も多くなっています。一方で、「生成AIと何が違うのか」「どこまで人の手を離れて業務を任せられるのか」といった点が分かりづらく、導入判断に迷っている方も少なくありません。
特に、DX推進部門や企画部門、現場の運用部門にとっては、言葉のイメージだけで判断するのではなく、業務でどのように使われ、どこに注意すべきかを正しく理解することが重要です。
本記事では、自律型AIエージェントの基本的な考え方を整理しながら、生成AIや従来のチャットボットとの違い、活用時のポイントや限界について解説します。記事を通して、自社業務に適したAIエージェントの設計や選定を考えるための判断軸を持っていただくことを目的としています。
Index
自律型AIエージェントとは何か
自律型AIエージェントとは、あらかじめ与えられた目的やルールに基づき、状況に応じた判断や処理を行うAIの仕組みを指す言葉として使われています。ただし、ここで言う「自律」は、人間のように自由に判断・学習し続ける存在を意味するものではありません。
実際の業務で使われるAIエージェントは、
- 目的やゴールは人が定義する
- 判断の基準や制約条件も人が設計する
- その範囲内でAIが処理や選択を行う
という前提で成り立っています。
つまり、自律型AIエージェントは現状の仕組みでは、人が設定した目標やルールの範囲内で判断・処理を行うものであり、人の管理や設計の外で勝手に動くものではありません。
今回は、AIエージェントの仕組みと特徴について解説します。生成AIとの違いやAIエージェントの種類、AIエージェントを導入するメリットも紹介。
生成AI・チャットボットとの違い
自律型AIエージェントを理解するうえで、生成AIや従来型チャットボットとの違いを整理しておくことは欠かせません。
生成AIは、質問に対して文章や画像などを生成することを主な役割としています。高い表現力や柔軟な回答が特徴ですが、基本的には「聞かれたことに答える」存在です。
一方、従来型のチャットボットは、FAQやシナリオに基づいて応答を返す仕組みで、想定された範囲の問い合わせ対応を得意とします。ただし、複数の業務をまたいだ処理や、状況に応じた判断には限界があります。
自律型AIエージェントは、これらとは異なり、タスクの遂行を前提に設計される点が特徴です。単なる回答にとどまらず、業務フローの一部を担い、次の処理につなげる役割を持ちます。
業務で使われるAIエージェントの設計イメージ
業務でAIエージェントを活用する場合、「どこまでをAIに任せ、どこを人が担うのか」を明確にする必要があります。
一般的な設計では、
- 業務の目的や完了条件を定義する
- 判断が必要なポイントを整理する
- 例外時やエラー時の対応を決める
といった工程を踏んだうえで、AIが処理を担当します。このように、自律的に見える振る舞いも、実際には人が設計したルールや業務構造の上で成立していることが分かります。AIエージェントは、設計の質によって成果が大きく左右される仕組みだと言えるでしょう。
ビジネスで期待される効果と適切な期待値
自律型AIエージェントを業務に取り入れることで、さまざまな効果が期待されます。ただし、過度な期待を持たず、できること・できないことを整理しておくことが重要です。
代表的な効果としては、以下があります。
- 業務対応の標準化による品質の安定
AIエージェントは、複数の判断基準や業務フローを統合して処理できます。人によって異なる判断が発生しやすい業務でも、設定されたルールやシナリオに基づき一貫した対応を実現します。 - 処理スピードの向上や複数業務の同時支援
単一の問い合わせだけでなく、複数のタスクやチャネルにまたがる処理もAIエージェントなら同時に進められます。これにより、対応件数やスピードが大幅に向上します。 - 業務フローの可視化と改善ポイントの発見
AIエージェントは業務プロセスの中でどの判断を行い、どの情報を参照したかをログとして残せます。この情報を活用すれば、属人化していた判断や手順の違いを整理でき、業務改善の材料として活用できます。 - 複数AIの連携による柔軟な対応
単体AIでは対応が難しい複雑な業務でも、役割ごとに分かれたAIエージェント同士が連携することで、全体の処理を効率的かつ安定的に進めることが可能です。
一方で、AIが自ら業務を改善したり、判断基準を自動で最適化し続けたりするわけではありません。業務要件の見直しや改善は、人が主体となって行う必要があります。この点を理解したうえで導入することで効果を最大限に活かすことができます。
導入時に押さえておきたいポイントと留意点
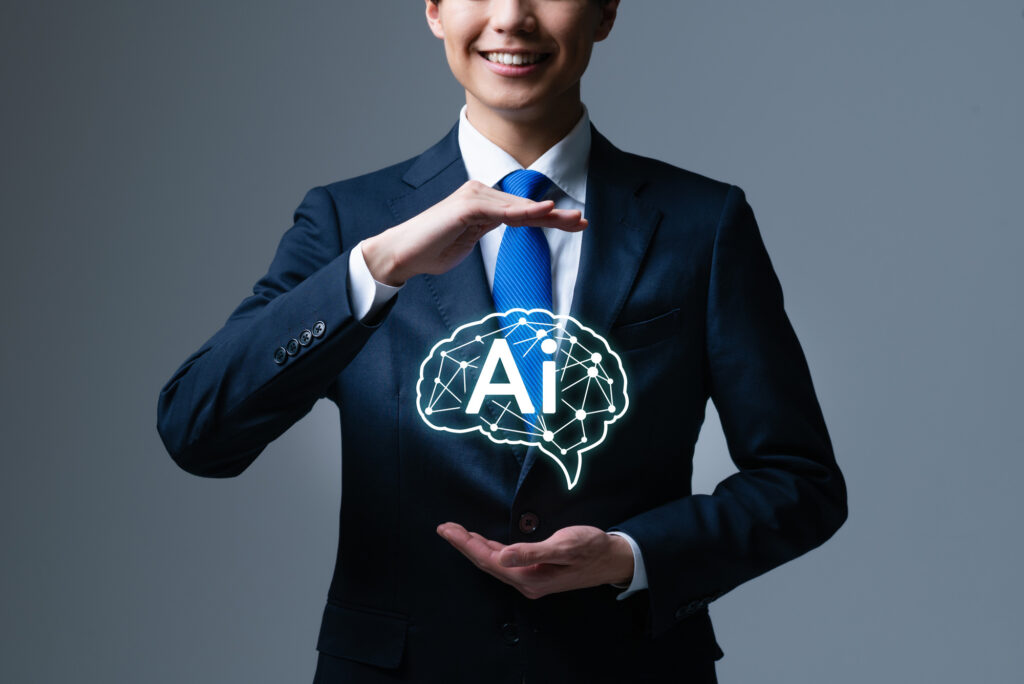
自律型AIエージェントの導入では、技術面だけでなく運用面の検討も欠かせません。現場で期待通りに活用するためには、以下のポイントを事前に整理しておくと効果的です。
- 学習や判断に使うデータの品質
入力データが偏っていたり誤りが多いと、AIの判断精度も低下します。現状のデータを整理し、必要であれば前処理やクレンジングを行いましょう。 - 業務ルールの明確さ
どの業務をAIに任せ、どこで人が介入するかを明確化しておくことが重要です。フロー図やチェックリストで役割分担を可視化すると、設計ミスを防げます。 - 人による最終確認や例外対応の設計
例外や未対応のケースが発生した際のフローを事前に定義しておくことで、運用中の混乱を避けられます。誰が判断するのか、どのタイミングで介入するのかも明示しましょう。 - 段階的な適用
導入初期からすべての業務を任せるのではなく、影響の少ない業務や一部業務からテスト的に導入し、結果を確認しながら範囲を拡大するのが現実的です。
これらを踏まえ、現状の運用体制や業務フローと照らし合わせながら設計・試験運用を行うことで、導入後に期待した効果を得やすくなります。
業務全体を支えるAIの構成を考える

導入時に押さえておきたいポイントや留意点を整理したうえで、次に考えるべきは「AIをどのように配置して業務全体を支えるか」という設計の視点です。現状の業務では、問い合わせ対応や情報検索、判断、次の業務への引き継ぎなど、複数の工程が連続しています。単体のAIにすべての工程を任せると、設計や運用の負荷が高まり、期待した成果を出すのが難しくなるケースがあります。
たとえば、顧客対応業務を例に考えると、次のような流れがあります。
- 顧客からの問い合わせ内容を把握する
- 必要な情報を社内システムやデータベースから検索する
- 適切な回答を判断し、提供する
- 必要に応じて担当者や他部門に引き継ぐ
単体AIだけでこれをすべて担おうとすると、判断や処理の範囲が複雑化し、例外や想定外ケースへの対応も難しくなります。また、運用上の負荷が増え、効果が安定しにくいという課題も生まれます。
そのため近年注目されているのが、業務を細かく分解し、役割ごとにAIを担当させて連携させる構成です。たとえば、情報検索に特化したAIと応答生成に特化したAIを組み合わせることで、単体AIでは難しい業務フロー全体の支援が可能になります。こうすることで、各AIの役割が明確になり、運用も段階的に改善しやすくなります。現状の業務フローや運用体制に合わせて、どの工程をAIに任せ、どの工程を人が担うかを明確に設計することが、実務で安定してAIを活用する鍵となります。
業務に適したAIエージェントを設計・選定するために
自律型AIエージェントは、業務を人の手から完全に切り離す存在ではなく、設計された枠組みの中で業務を支援・自動化する仕組みです。重要なのは、「自律」という言葉のイメージではなく、自社の業務にどのように組み込み、どう運用するかという視点です。
単体AIでは対応しきれない業務に対しては、複数のAIを役割分担させて連携させる設計が有効になるケースもあります。こうした考え方を具体的に形にしたものが、CAT.AI マルチAIエージェントです。音声対応を重視する場合は CAT.AI マルチAIエージェント for Voice、チャットやテキスト業務を中心とする場合は CAT.AI マルチAIエージェント for Chatといった形で、業務特性に合わせた設計が可能です。
より具体的な活用イメージや導入検討の参考として、紹介資料をご覧いただくことで、どの業務にどのようにAIエージェントを組み込めるのかを具体的に把握できます。AIエージェント導入を検討する際の判断材料として、ぜひ活用してみてください。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。