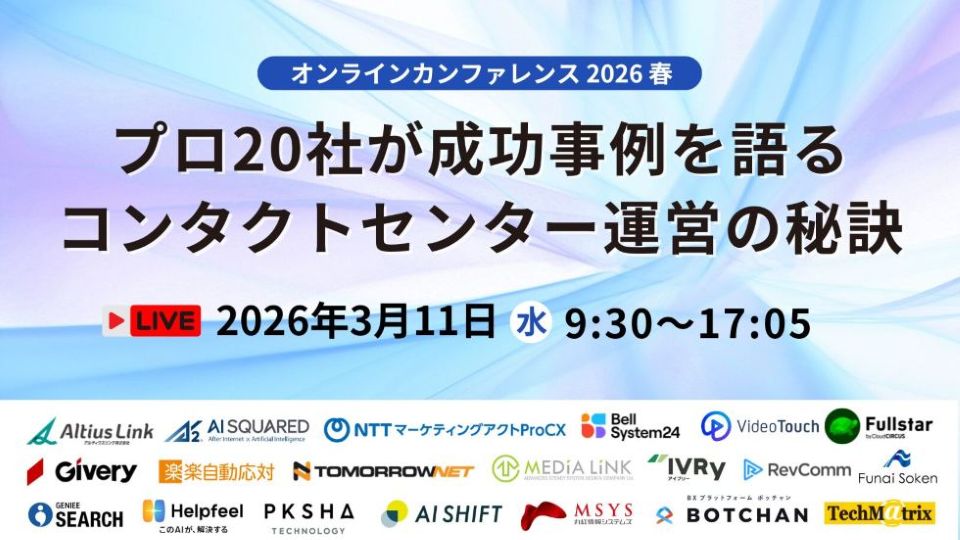バーチャルアシスタントは業務でどう使われるのか|企業活用の考え方

企業のDX推進や業務効率化が進む中で、「バーチャルアシスタント」という言葉を目にする機会が増えています。問い合わせ対応や業務受付、社内サポートなど、日々発生する定型的なコミュニケーション業務を支える手段として、導入を検討している企業も少なくありません。
一方で、生成AIやチャットボット、ボイスボットなど関連する技術や用語が増え、「自社業務ではどのように使えるのか」「どこから検討すべきなのか」と悩むケースも多いのではないでしょうか。
本記事では、企業利用の視点からバーチャルアシスタントの役割や活用シーンを整理し、導入によって得られる効果や業務設計の考え方を解説します。あわせて、バーチャルアシスタントを業務に取り入れる際に、どのような観点で検討を進めるとよいのかについても触れていきます。
Index
バーチャルアシスタントとは?いま企業で注目される理由
バーチャルアシスタントとは、音声やテキストによる対話を通じて、ユーザーからの問い合わせ対応や業務受付、案内業務などを支援する仕組みを指します。企業向けに活用される場合は、単なる会話機能にとどまらず、業務ルールやFAQ、システム連携などを組み合わせ、日常業務の一部を担う存在として位置づけられることが一般的です。
こうしたバーチャルアシスタントが企業で注目される背景には、以下のような要因があります。
- 問い合わせ件数の増加により、対応業務の負荷が高まっている
- 人材不足や属人化により、対応品質の平準化が求められている
- DX推進の一環として、定型業務のデジタル化・自動化が進んでいる
特に、コールセンターやカスタマーサポート、社内ヘルプデスクなどでは、対応内容がある程度パターン化されている一方で、件数が多く、人手だけでの対応に限界を感じているケースも少なくありません。そのような業務領域において、バーチャルアシスタントは業務を支える選択肢の一つとして検討されるようになっています。
AIエージェント時代におけるバーチャルアシスタントの位置づけ
AI活用が進む中で、バーチャルアシスタントはAIエージェントと並んで語られることが増えています。企業で導入を検討する際には、それぞれの役割を業務との関係性から整理しておくことが重要です。
バーチャルアシスタントは、問い合わせ対応や業務受付など、特定の業務領域において、対話を通じて業務を支える仕組みとして活用されています。一方、AIエージェントは、複数の業務やプロセスを横断的につなぎながら業務を進める仕組みとして位置づけられることが多くなっています。バーチャルアシスタントとAIエージェントは、それぞれ次のような仕組みとして位置づけられます。
- バーチャルアシスタント:特定業務において対話・受付・案内を行う仕組み
- AIエージェント:複数業務やプロセスを横断的につなぐ仕組み
両者が同じ文脈で語られやすい背景には、いずれも対話を起点に業務と関わる点があります。活用を検討する際には、業務範囲が限定的か横断的か、対話を中心に支援したいのかといった観点から整理することで、バーチャルアシスタントの位置づけを捉えやすくなります。
バーチャルアシスタントはどんな業務で使われているのか
バーチャルアシスタントの活用を検討する際には、実際にどのような業務で使われているのかを把握することが重要です。ここでは、企業でよく見られる活用シーンを紹介します。
問い合わせ対応・一次受付での活用
最も代表的な活用例が、顧客や利用者からの問い合わせ対応です。バーチャルアシスタントは、あらかじめ整理された情報や業務ルールに基づき、問い合わせ内容を受け止め、必要な案内や振り分けを行います。
- 営業時間や手続き方法など、定型的な案内対応
- よくある質問への即時回答
- 問い合わせ内容の整理と担当窓口への振り分け
一次対応を担うことで、人は個別判断や対応が必要なケースに集中しやすくなります。
定型的な手続き・案内業務としての活用
申請や予約、利用手順の案内など、対応フローが決まっている業務もバーチャルアシスタントと相性のよい領域です。対話を通じて必要事項を確認しながら進めるため、利用者の迷いや手戻りを減らしやすくなります。
- 各種申請・予約の手順案内
- サービス利用方法や操作手順の説明
- 必要書類や条件の確認
業務単位で切り出しやすく、既存業務に組み込みやすい点が特徴です。
社内問い合わせ・業務窓口としての活用
バーチャルアシスタントは、社内向けの問い合わせ対応にも活用されています。社内業務では問い合わせ内容が似通うことが多く、担当部門の負荷が集中しやすい傾向があります。
- 社内ルールや申請方法に関する問い合わせ対応
- IT・総務などの一次受付
- 複数の問い合わせ窓口の集約
特定業務の窓口として対話対応を担い、日常業務を支える役割として活用されるケースが多く見られます。
クラウドサービスを社内外で活用する際はセキュリティ対策についても重要ですので、以下も参考にご覧ください。
参考:クラウドサービスを安全に活用するためのセキュア接続とは|ZEAD
バーチャルアシスタントの導入効果と業務設計のポイント

バーチャルアシスタントの導入は、単に対応を自動化することが目的ではありません。
どのような効果が得られるのか、またその効果を安定して引き出すためにどのような業務設計が必要かを整理しておくことが重要です。
ここではまず導入によって期待できる効果を確認し、その後に設計の考え方を見ていきます。
バーチャルアシスタント導入によって得られる効果
バーチャルアシスタントは、日常的に発生する定型業務の一次受付や案内を担うことで、運用面での改善効果が見えやすいのが特徴です。単なる自動化とは異なり、対話を通じて利用者の要望を整理し、次の業務ステップへスムーズにつなぐことができます。
業務負荷の軽減と対応の効率化
- 対話形式で問い合わせ内容を聞き取り、必要に応じて担当者や関連窓口へ自動で振り分け
- 担当者は個別判断や例外対応に集中でき、日常的な手続き対応にかかる時間を削減
対応品質の安定化
- 定型業務のフローや案内内容を整理した上で対話を実行するため、誰が対応しても一定の品質を維持
- 利用者が迷わず用件を進められる体験を提供し、窓口業務のばらつきを抑制
利用者体験の向上
- 24時間対応やステップごとの案内により、問い合わせ完了までの手戻りを減らす
- 単なるFAQやマニュアル参照ではなく、会話を通じて必要な情報や手続きに誘導
効果を出すための業務設計の考え方
前章で紹介した効果を継続的に引き出すためには、どの業務にどのようにバーチャルアシスタントを活用するかを事前に整理しておくことが欠かせません。業務特性や対応内容に応じて設計することで、導入後の運用をスムーズにし、効果を最大化できます。
バーチャルアシスタントで成果が出やすい業務
バーチャルアシスタントが効果的に活用できる業務には、いくつかの共通点があります。特に次のような特徴を持つ業務は、導入後に成果が見えやすく、現場への定着も進めやすくなります。
- 問い合わせ内容や手続きの流れがある程度決まっている
- 判断基準や業務ルールを文章として整理できる
- 件数が多く、対応工数が積み上がりやすい
人とバーチャルアシスタントの役割分担
また、バーチャルアシスタントと人が協働する運用設計も重要です。役割を整理しておくことで、業務全体の流れをスムーズにし、効果を安定して引き出すことができます。一般的には、次のように分けると効率的です。
- 一次対応や受付、基本的な案内はバーチャルアシスタントが担当
- 個別判断や例外対応が必要なケースは人が担当
こうすることで、業務全体の流れがスムーズになり、導入効果を最大化できます。
バーチャルアシスタント導入を成功させるためのポイント
最後に、バーチャルアシスタントを業務で活用していくうえで、あらかじめ整理しておきたいポイントをまとめます。バーチャルアシスタントは、特定業務の「窓口」や「一次受付」として機能することが多いため、その特性を踏まえて検討することが重要です。
導入目的と業務範囲をどう定めるか
まずは、どの業務の窓口を担わせるのかを明確にしておくことが欠かせません。問い合わせ削減や受付業務の効率化など、導入の狙いと対象業務を整理しておくことで、バーチャルアシスタントに任せる役割と人が対応すべき範囲を切り分けやすくなります。
UX設計と改善を前提にした運用
バーチャルアシスタントは、対話を通じて業務を受け付け・案内する仕組みであるため、利用者が迷わず用件を完了できる体験設計が重要になります。導入後も、問い合わせログや対話の途中離脱などを確認しながら、窓口業務としての使いやすさを継続的に見直していくことが求められます。
部分導入から業務全体へ広げる視点
バーチャルアシスタントは、特定業務の一次受付や案内窓口として導入しやすい特性があります。最初から広範囲をカバーしようとせず、問い合わせ対応や業務受付など、効果が見えやすい窓口業務から導入し、運用状況を見ながら活用範囲を広げていく進め方が現実的です。
バーチャルアシスタントから広がる、次のAI活用
本記事では、企業におけるバーチャルアシスタントの役割や活用シーン、導入によって得られる効果、業務設計の考え方について整理してきました。バーチャルアシスタントは、問い合わせ対応や業務受付など、特定業務の窓口として対話を担い、日常業務を支える存在として活用されるケースが多く見られます。
一方で、こうした窓口業務を起点に、複数の業務やシステムを連携させていく考え方として、AIエージェントやマルチAIエージェントへの関心も高まっています。バーチャルアシスタントで培った業務整理や対話設計は、より広い業務プロセスをつなぐAI活用へと発展させやすい土台にもなります。
CAT.AI マルチAIエージェントは、対話を起点に、業務処理やシステム連携までを含めた一連の流れを支援できる仕組みです。バーチャルアシスタントで対応していた窓口業務を、次の業務アクションへ自然につなげたい場合にも活用できます。
バーチャルアシスタントの導入や、その先のAI活用を検討するうえで、具体的な設計や活用イメージを知りたい方は、CAT.AI マルチAIエージェントの資料やホワイトペーパー、導入事例集をご覧ください。自社業務にどのように適用できるかを検討するヒントとしてご活用いただけます。
企業の皆さまやユーザーの皆さまのIT活用を円滑化する総合的なコミュニケーションプラットフォーム、「CAT.AI」の紹介資料です。CAT.AI マルチAIエージェントは、ユーザーの意図に合わせて最適なAIを組み合わせて対応し、問い合わせから業務処理まで一貫して対応を完結します。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。