RAGとファインチューニングの違いは?生成AIのカスタマイズ手法を徹底比較

生成AIを自社業務で活用しやすくする代表的なアプローチに「RAG」と「ファインチューニング」があります。これらはAIの回答精度を高める代表的な手法ですが、導入コストから日々の更新性、得意な業務まで大きく異なる点もあります。
本記事では、2つのカスタマイズ手法を徹底比較し、AI活用を成功に導くためのポイントを分かりやすく解説するので、ぜひ最後までご一読ください。
Index
RAGとファインチューニングとは?
生成AIをビジネスで活用する上で、「RAG」と「ファインチューニング」は欠かせない主要なカスタマイズ手法です。ここでは、それぞれの仕組みや特長を解説し、どのような場面で有効かを整理していきます。
RAGは外部知識を活用して応答を生成する仕組み
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、生成AIが外部の知識を検索・参照しながら応答を作る仕組みです。モデル単体では持っていない情報を知識ベースから取得し、それを組み合わせて回答を導きます。学習済みモデルの知識に縛られず、最新情報を反映できるのが特長です。
具体的には、FAQ、社内マニュアル、製品仕様書といった文書を知識ベースに組み込み、質問に対して該当部分を検索したうえで自然な文章にまとめます。例えば「最新の勤怠ルールは?」と問われれば、更新済み規定をすぐに返せます。
更新も容易で、文書を差し替えるだけで回答が改善されるため、大規模な再学習は不要です。変化の多い業務や多様な質問に対応する場面で強みを発揮します。
ファインチューニングはモデルそのものを再学習させる手法
ファインチューニングは、AIモデルに特定データを追加学習させ、専門領域に特化した応答を可能にする方法です。モデルのパラメータを調整するため、外部検索なしでも専門的かつ安定した回答を返せるのが魅力です。
医療分野では臨床記録を学習させることで、診療業務の補助に活かすことができます。法律分野では契約書や判例データを学習させることで、文体や用語の統一された文書生成が可能です。こうした応答は、汎用モデルより安定性が高くなる傾向があります。
ただし再学習にはGPUや高度な知識が必要で、準備や検証にコストもかかります。また、一度学習させた内容を更新するには再学習が不可欠なため、変化の少ない領域に適してるといえるでしょう。
共通点は業務に即した回答をするAIの実現
RAGとファインチューニングは方法こそ違いますが、どちらも「業務に最適な回答を返すAI」を目指しています。汎用モデルは幅広い知識を持ちますが、実務で必要な最新情報や専門知識まではカバーできないため、この2つの手法が活用されます。
RAGはコールセンターや社内ヘルプデスクなど、最新文書を参照しながら答える業務に強く、一方、ファインチューニングは専門用語が多く文体の一貫性が求められる業務に適しています。いずれも「汎用AIでは対応しにくい課題を解決する」点が共通しているといえるでしょう。
RAGとファインチューニングの違いとは?
ここでは、導入・運用コスト、保守・更新性、精度・安定性、リアルタイム性、適する業務の観点から両者の違いを整理します。
| 比較項目 | RAG(Retrieval-Augmented Generation) | ファインチューニング(Fine-Tuning) |
|---|---|---|
| 導入・運用コスト | 初期構築が比較的容易で、モデルそのものの再学習は基本的に不要のため低コストで始めやすい。ただし検索基盤やインフラ維持の費用は発生する。 | 初期学習にGPUや専門知識が必要で準備コストは高め。一度学習を終えれば、運用環境やモデルサイズに応じておおむね安定した推論コストで利用可能。 |
| 保守・更新性 | ナレッジベースを更新すればほぼリアルタイムで反映可能。情報改訂に素早く対応できる。 | 知識を反映させるには再学習が必要。更新には時間とリソースを要する。 |
| 精度・安定性 | 外部文書を参照するため幅広い質問に対応可能。ただし文脈が曖昧だと回答の一貫性に欠ける場合がある。 | 特定分野では高精度で安定した応答が可能。専門用語や文体を一貫して反映できる。 |
| リアルタイム性 | 外部データをほぼリアルタイムでに取り込み、最新情報を回答に反映可能。変化の多い環境に強い。 | 再学習が必要なため更新サイクルは遅め。リアルタイム性は限定的。 |
| 適する業務 | FAQ対応、社内ヘルプデスク、コールセンターなど、文書を参照しながら回答する業務。更新頻度が高い環境にも対応しやすい。 | 医療・法務・金融など高い専門性が必要な分野。内容の変化が少なく、安定した応答品質が求められる業務で効果を発揮しやすい。 |
RAGは柔軟性と迅速性に優れ、変化の早い業務や幅広い質問に対応するケースに適しています。FAQ対応や社内ヘルプデスク、コールセンター業務など、知識を常に更新しながら運用する場面に強みをもつのが特長です。
一方でファインチューニングは、専門性が高い領域において安定した応答を返せることが得意です。医療、法律、金融など正確性と一貫性が特に求められる分野に適しており、知識の変化が少ない業務においては長期的に高い効果を発揮します。
両者は対立する手法ではなく、目的や環境に応じて使い分けるものです。実務では、RAGを基本としつつ一部の重要領域にファインチューニングを組み合わせる「ハイブリッド構成」も有効な選択肢となります。
RAGとファインチューニングを導入するときの進め方
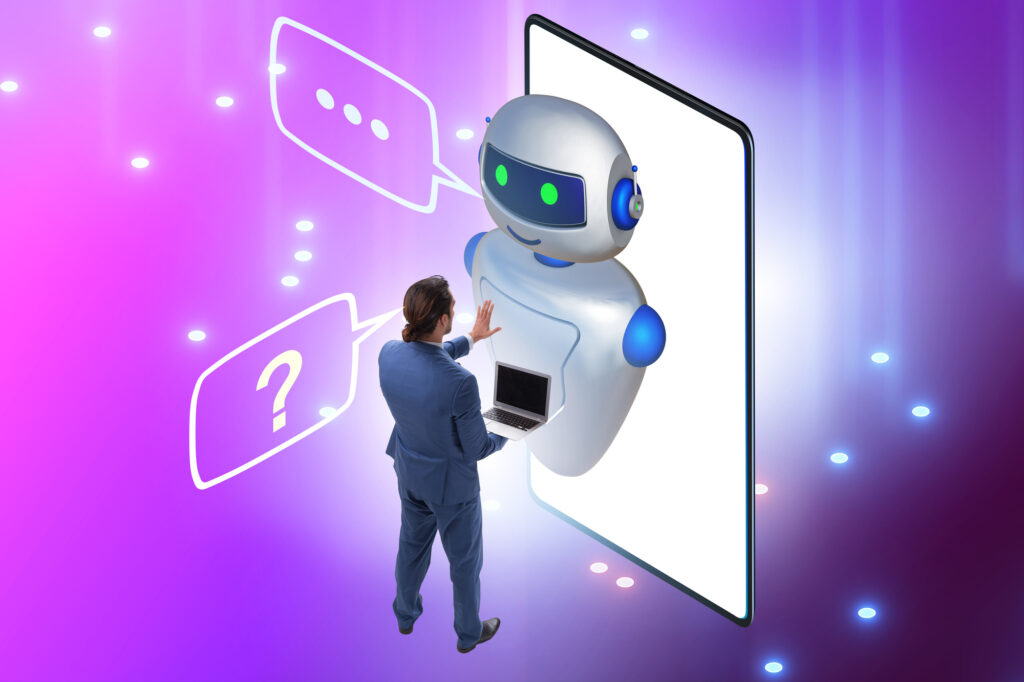
ここでは、導入にあたって検討すべき視点と進め方のステップをまとめます。目的や準備段階、リソース、試験運用といった観点から、各手法の適合性を見極める方法を解説します。
目的と課題を明確にする
最初に取り組むべきは、AI導入で解決したい課題や期待する成果を明確にすることです。
- 変化する情報をすぐに反映したい → RAGが有効
- 一貫性のある専門的な回答を重視したい → ファインチューニングが有効
ゴールが曖昧なまま進めると、導入後に方向転換が必要になり余計なコストを招く恐れがあります。導入前にゴールを明確化しておくことで、導入効果を最大限に引き出せます。
既存データやナレッジの有無を確認する
次に自社の情報資産を整理してみましょう。
- FAQ・マニュアル、社内ドキュメントが豊富 → RAG向き
- 会話ログ・専門用語辞書、業務特化データが充実 → ファインチューニング向き
導入前に棚卸をすることで、どちらのアプローチが有効かを検討しやすくなります。また、必要なデータが不足している場合は、導入前に整備を進めておくことも重要です。
開発リソース・スキルを見極める
AI導入にはリソース面の制約が発生します。
- RAG:SaaS型のソリューションを活用すれば比較的容易に導入可能
- ファインチューニング:GPU環境や機械学習スキルが求められる場合が多い
高度なカスタマイズを検討する場合は、早めに外部ベンダーや専門家と連携することが現実的です。
小さく試して改善を重ねる
AI導入を成功させるには、最初から全面展開するのではなく、PoC(概念実証)や限定的な業務への試験導入から始めるのが理想です。
- RAG:小規模データでも効果検証でき、課題や改善点を明確にしやすい
- ファインチューニング:対象領域を絞り、段階的にデータの質を確認しながら精度を高められる
いずれも小さく始めやすい手法なので、自社の状況に合わせて適切なアプローチを選ぶことが大切です。小さな成功を積み重ねることで社内の理解や協力も得やすくなり、本格導入への移行もスムーズになるでしょう。
信頼できるパートナーと進める
最後に、外部の信頼できるパートナーと連携することは導入の成否を左右する大きな要素です。特にRAGとファインチューニング双方に対応できるベンダーを選べば、自社の現状に合わせた導入支援から将来的なハイブリッド運用まで一貫して伴走してもらえます。
パートナーが持つ知見を活かすことで、導入スピードが上がるだけでなく、リスクを抑えた運用改善も実現可能です。社内のリソースだけに頼らず、専門家の支援を得ながら柔軟に進めることが、長期的な成功につながります。
RAGとファインチューニングで業務効率化を図ろう
RAGとファインチューニングは、それぞれ異なる強みを持ちながら、共通して業務効率化を後押しする技術です。
RAGは外部データを即時に取り込み、変化の多い業務や最新情報が求められる場面に適しています。一方、ファインチューニングは特定領域に特化した再学習により、高精度で安定した応答を実現し、専門性が高い業務に向いています。
両者を組み合わせれば、人手に頼っていた作業も精度とスピードを両立して自動化できるでしょう。さらに、トゥモロー・ネットが提供する「CAT.AI CX-Bot」や「CAT.AI マルチAIエージェント」は、問い合わせ対応から処理完了までを一貫して支援し、効率化だけでなく顧客体験の向上や事業成長にもつながります。
企業の業務効率化を次のレベルへと引き上げるために、ご興味のある方は、ぜひ下記リンクから資料をご覧ください。
企業の皆さまやユーザーの皆さまのIT活用を円滑化する総合的なコミュニケーションプラットフォーム、「CAT.AI」シリーズのご紹介資料です。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。








