AIエージェントと生成AIはどう違う?初心者向けに徹底解説
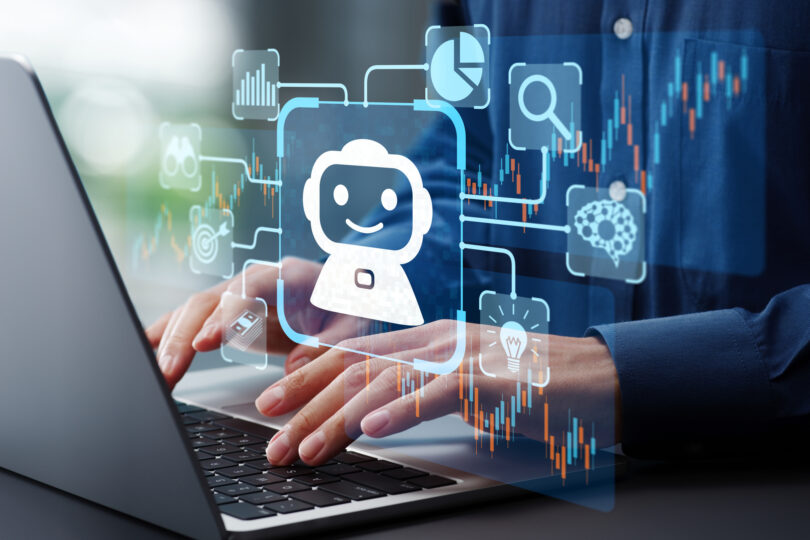
最近よく耳にする「AIエージェント」と「生成AI」。どちらもAIの一種ですが、役割や仕組みには大きな違いがあります。この違いを理解しないままAIツールを導入すると、期待した効果が得られないかもしれません。
この記事では、AIの初心者の方でも違いがわかるよう、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。最後までお読みいただければ、それぞれの役割や活用シーンが明確になり、自社の業務にどうAIを取り入れるべきか、そのヒントが見つかるはずです。
Index
AIエージェントと生成AIの根本的な違いとは?
簡単に言うと、生成AIは「何かを創り出す」ことを手助けするAIであり、AIエージェントは「目的を達成するために行動する」AIです。
ここでは、それぞれの役割と仕組みについて、もう少し詳しく見ていきましょう。
生成AIは「創造」をサポートするAI
生成AIは、テキスト、画像、音楽、動画など、新しいコンテンツを「生成」することに特化したAIです。 「創造の手助けをするAI」とイメージすると良いでしょう。
多くの人が活用しているChatGPTやMidjourneyなどは、この生成AIの代表例です。
主な役割
新しいコンテンツを生成し、人間のクリエイティブな作業や情報整理をサポートします。具体的には、ブログ記事の作成、デザイン案の生成、長い文章の要約や翻訳などが得意です。
仕組み
生成AIは、膨大な情報のパターンを学習し、ユーザーの指示に基づいて、新しい文章や画像を生成します。
AIエージェントは「行動」を自動化するAI
AIエージェントは、人間から与えられた目的を達成するために、ユーザーの指示に基づき必要なステップを自動で判断し実行するAIです。 単にコンテンツを作るだけでなく、情報を検索したり、複数のツールを操作したり、他のAIと連携したりと、まるで人間のアシスタントのようにタスクをこなします。いわば、「行動の手助けをするAI」です。
AIエージェントの代表例にはAutoGPT、CAT.AIマルチAIエージェントがあります。
主な役割
目的達成のためにユーザーの指示に基づきタスクを自動で実行し、複雑な作業の管理や効率化をサポートします。
複数のステップにまたがる業務や、複数のソフトウェアを横断する作業の自動化が得意です。
仕組み
AIエージェントは、ユーザーの指示に基づき、与えられた目的を達成するために必要な行動を計画・実行します。
例えば「今日の株価情報を集めてレポートを作成する」と指示すると、Webサイトから情報を取得・整理し、レポートを完成させるといった一連のプロセスを実行します。
【具体例で比較】生成AIとAIエージェントの得意なこと

両者の違いをより明確にするために、具体的な活用事例を見ていきましょう。それぞれの得意分野を理解することで、自社のどの業務に適用できるかイメージしやすくなります。
生成AIの活用事例:クリエイティブ作業や情報整理を効率化
生成AIは「創造」をサポートする場面で力を発揮します。
- 広告のキャッチコピーを複数パターン生成し、ABテストに活用
- 自然な文章で回答するチャットボット(ユーザーの質問に応じて文章を生成)
- ブログ記事やSNS投稿文の草案作成
- 商品モックアップやデザイン案の生成
- 文章の要約や翻訳
AIエージェントの活用事例:複数ステップの定型業務を自動化
AIエージェントは「行動」を自動化し、一連のプロセスを効率化する場面で活躍します。
- 市場調査→レポート作成→メール送信など、一連の業務プロセスを自動化
- スケジュール管理や出張手配、レストラン予約などパーソナルアシスタント業務
- 複数のデータソースを分析し、特定の傾向やパターンを発見して通知
生成AIとAIエージェントの違い比較表
ここまで見てきたように、生成AIとAIエージェントは得意な領域が明確に異なります。両者の特徴や使い分けをさらにわかりやすくするため、以下の表で整理しました。
| 特徴 | 生成AI | AIエージェント |
| 主な機能 | 新しいコンテンツの生成 | 目的達成のために手順を考えて行動 |
| 得意なタスク | クリエイティブな作業、コンテンツ作成、要約 | 複雑なタスクの自動化、情報収集、計画立案 |
| 出力形式 | テキスト、画像、音声、動画など | タスク完了後のレポート、実行されたアクションの記録、データ取得・整理結果の表示 |
| イメージ | 「創造の手助け」 | 「行動の手助け」 |
| 代表例 | ChatGPT、Midjourney、Stable Diffusion | AutoGPT、BabyAGI |
どちらを選ぶべき?AI導入の判断基準
AIを選ぶときは、「単発の作業を効率化したいのか」「複雑なタスク全体を自動化したいのか」を基準にすると分かりやすくなります。
生成AIが向いているケース
- 単発の作業や短時間で文章・デザインなどを作成したいとき
例:メールの返信文作成、会議の議事録要約、プレゼン資料のデザイン案出し - 大量の情報を要約したり翻訳したりして効率化したいとき
例:海外の最新ニュース記事を日本語で要約して情報収集する - アイデア出しや下書きの作成をサポートしてほしいとき
例:新しいプロジェクトの企画アイデアをブレストする
AIエージェントが向いているケース
- 複数ステップにわたる作業をまとめて自動化したいとき
例:毎月の売上データを収集し、定型のレポートを作成して関係者に送るメール文案を作成する - 複数のツールやシステムを組み合わせて、目的を効率よく達成したいとき
例:顧客からの問い合わせメールの内容を解析し、内容に応じて担当者を割り振り、日時の候補を提案する - 継続的に情報をチェックし、条件に応じたアクションを行いたいとき
例:競合他社のWebサイトを定期的に巡回し、価格変更があれば通知する
さらなる業務効率化へ!生成AIとAIエージェントの連携が生む可能性
生成AIとAIエージェントは、それぞれ単独でも非常に有用ですが、連携させることで、さらに高度なタスクを自動化できます。
連携によるメリットと具体例
生成AIが「コンテンツを作る」、AIエージェントが「作業を進める」という役割分担をしながら連携することで、人間が手作業で行っていた複雑な業務を効率的に自動化できます。
例えば、「競合A社の市場動向を調査して、レポートとプレゼン資料を作成して」という指示をAIに与えたとします。
- AIエージェントが行動(情報収集・整理)
- Web検索ツールを使い、最新の市場データを収集
- 競合A社のSNSやプレスリリースをチェック
- 収集したデータを整理してまとめる
- 生成AIが創造(コンテンツ生成)
- 整理されたデータと分析結果を基に、レポートの文章を生成
- プレゼン資料の構成やスライドごとのテキスト・デザイン案を生成
- AIエージェントが行動(共有)
- 作成されたレポート・資料を指定フォルダに保存
- 関係者に送るメール文案を作成し、提案
このように、それぞれの強みを活かすことで、これまで人間が多くの時間を費やしていた一連の業務プロセスを自動化し、生産性を大きく向上させることが可能になります。
AIエージェントと生成AIの未来
生成AIの登場で、AIは私たちの身近な存在になりました。そして今、AIエージェントの進化により、AIは単なる「ツール」から、作業の自動化を補助する「パートナー」へと変わりつつあります。生成AIとAIエージェントが連携し、より高度で複雑なタスクをこなすことで、私たちの働き方や生活はさらに効率化されるでしょう。
生成AIは文章や画像の「創造」を担当し、AIエージェントは複数ステップの作業や情報整理の「効率化」を担います。これらを適切に組み合わせることで、ビジネスや日々の業務は大きく変わります。
「文章作成だけでは終わらない業務プロセス」や「複数のAIツールを組み合わせた自動化」を実現したい場合、単一のAIでは限界があります。また、各AIを連携させるには専門知識や工数も必要です。これらの課題を解決できるのが、マルチAIエージェントです。
リードエージェントが指示を出し、複数のAIエージェントが高度に連携することで、業務プロセスの自動化を実現します。単一のAIエージェントでは対応が難しい複雑なタスクも、複数のAIエージェントが連携することで効率的に処理できます。
CAT.AI マルチAIエージェントの製品資料では、具体的な導入事例や活用シーン、どのようにAIエージェント同士が連携して複雑なタスクを処理しているかを紹介しています。記事で理解した「創造」と「行動」の役割を、実際の業務にどう適用できるかをイメージするためにも、ぜひご覧ください。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。









