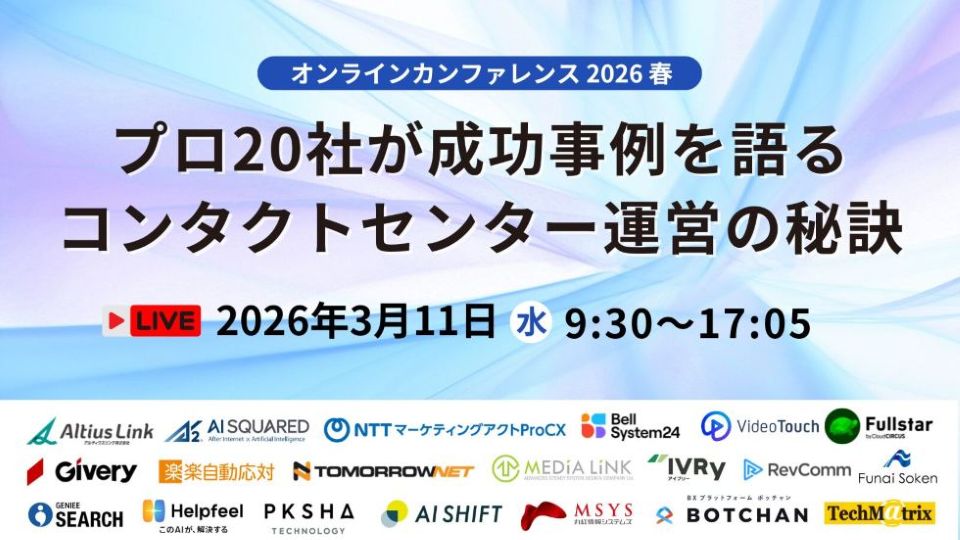対話型AIとは?特性と限界を整理し、業務に活かす考え方

近年、業務効率化や顧客対応の高度化を目的に「対話型AI」を導入・検討する企業が増えています。ChatGPTに代表される汎用的なテキスト対話型AIは、資料作成やナレッジ活用などで成果を上げる一方、「そのまま顧客対応や業務フローに使えるのか?」と疑問を感じている担当者も少なくありません。
実際の業務現場では、問い合わせ内容の聞き取り、本人確認、システム連携を伴う手続きなど、単純な対話だけでは完結しないケースが多く存在します。そのため、対話型AIは「どれを導入するか」ではなく、「業務のどこで、どの役割を担わせるか」という設計視点が重要になります。
本記事では、対話型AIの基本的な考え方から、テキスト対話型AI・音声対話型AIそれぞれの特性と限界を整理し、業務に応じた使い分け・組み合わせの判断軸を解説します。
Index
対話型AIとは?業務利用で求められる役割
対話型AIとは、人とやり取りをしながら情報提供や業務支援を行うAIの総称です。ChatGPTの普及により、会話できるAIそのものに注目が集まりましたが、企業利用で重要なのは「会話できること」ではありません。
企業における対話型AIは、問い合わせ対応や手続きの開始など、業務の入口として人とシステムをつなぐ役割を担います。そのため、対話はゴールではなく、業務を進めるための手段として設計されているかどうかが重要になります。
近年は、業務の高度化や人手不足を背景に、対話型AIを単体で完結させるのではなく、業務全体の中で役割分担させる発想が求められるようになっています。
汎用テキスト対話型AIの強みと、業務適用時の注意点
汎用テキスト対話型AIが得意とする業務
ChatGPTに代表される汎用的なテキスト対話型AIは、自然言語の理解・生成を強みとし、主に次のような業務で活用されています。
- 社内資料や議事録の要約・下書き作成
- 社内ナレッジをもとにした情報検索
- アイデア出しや検討時の壁打ち
これらは、AIが業務処理を担うというより、人の判断や作業を補助する用途であり、比較的導入しやすい点が特徴です。
顧客対応・業務フローで注意すべきポイント
一方で、顧客対応や業務フローにそのまま組み込む場合、次のような課題が生じやすくなります。
- 入力内容の曖昧さによる意図の取り違え
- 本人確認や業務ルールへの対応が難しい
- 対話の先でシステム処理につながらない
これらはAIの性能というより、業務設計と役割定義が不十分なまま導入してしまうことが原因であるケースが多く見られます。
テキスト対話型AIを活かすための考え方
汎用テキスト対話型AIを業務で効果的に活用するには、「何でも任せる」のではなく、得意な領域に役割を限定することが重要です。
たとえば、
- 人が最終判断を行う前の情報整理・下準備
- FAQやナレッジをもとにした一次対応
- 業務フローに入る前のヒアリングや分類
といった位置づけであれば、テキスト対話型AIの強みを活かしやすくなります。
次章では、テキストとは異なる特性を持つ音声対話型AI(ボイスボット)について、業務での役割と限界を整理します。
音声対話型AI(ボイスボット)が担う業務領域と限界
なぜ音声による対話はなくならないのか
チャットやWebフォームなどのデジタルチャネルが普及する一方で、電話による問い合わせ対応は多くの業界で依然として重要な役割を担っています。特に、緊急性の高い問い合わせや、操作に不慣れな顧客が多い業界では、音声による対話が選ばれやすい傾向があります。
企業側にとっても、電話対応は顧客との重要な接点である一方、対応負荷が高く、人材確保や教育の面で課題になりやすい領域です。そのため、音声対話型AI(ボイスボット)を活用し、一次対応や定型的な案内を自動化したいというニーズは根強く存在しています。
ボイスボットが得意とする業務領域
音声対話型AIは、あらかじめ設計されたフローに沿った対応を得意とします。特に、問い合わせ内容が比較的定型化されている業務では、一定の効果を発揮します。
代表的な活用例としては、次のようなものが挙げられます。
- 営業時間や手続き方法などの自動案内
- 用件の一次ヒアリングと振り分け
- 簡単な予約受付や変更対応
- オペレーターにつなぐ前の事前確認
これらの業務では、対応品質を一定に保ちつつ、オペレーターの負荷軽減につながる点が評価されています。
音声対話ならではの課題と限界
一方で、音声対話型AIには特有の難しさもあります。テキストと異なり、発話内容が曖昧になりやすく、誤認識が業務に影響を及ぼすケースも少なくありません。
具体的には、以下のような課題が挙げられます。
- 音声認識の誤りにより、意図しない分岐が発生する
- 数字や固有名詞の聞き取りが難しい
- 複雑な確認や分岐が続くと、利用者が迷いやすい
- 対話の途中で業務が止まり、人手対応に戻る
その結果、「導入したものの、利用率が伸びない」「結局オペレーター対応が増えてしまう」といった課題につながることもあります。
音声対話型AIを業務で活かすための視点
音声対話型AIを効果的に活用するには、音声だけで完結させようとしない設計が重要です。音声での対話はあくまで入口と捉え、必要に応じてテキストやシステム処理と連携させることで、業務全体の流れを止めにくくなります。
この視点を踏まえると、音声対話型AIは単独で使うものではなく、他のAIや仕組みと組み合わせて活用する存在として位置づけることが現実的です。
次章では、こうした背景を踏まえ、対話型AIを「使い分け」ではなく「組み合わせ」で考える理由と、その設計の考え方を整理します。
対話型AIは「使い分け」ではなく「組み合わせ」で考える
「どのAIを選ぶか」では解決しない理由
対話型AIの導入を検討する際、「テキスト対話型AIとボイスボットのどちらが良いのか」といった選び方をしてしまうケースは少なくありません。しかし実際の業務では、どちらか一方だけで完結するケースは限られています。
問い合わせ対応や手続き業務は、
- 内容の聞き取り
- 条件の確認
- システム処理
- 必要に応じた人手対応
といった複数のステップで構成されており、単一の対話型AIにすべてを担わせる前提自体が現実的ではない場合が多いためです。
業務を「対話・判断・処理」に分解して考える
対話型AIを業務に組み込む際は、まず業務を次のように分解して捉えることが有効です。
- 対話:顧客や社員から情報を受け取り、意図を把握する
- 判断:ルールや条件に基づいて次の対応を決める
- 処理:システム連携や手続きを実行する
テキスト対話型AIは「対話」や一部の「判断」に強みを持ち、音声対話型AIは電話チャネルでの「対話」に適しています。一方で、「判断」や「処理」を含む業務全体をスムーズにつなぐには、複数のAIや仕組みを連携させる設計が欠かせません。
対話の先で業務が止まる構造
対話型AI導入が期待した成果につながらない場合、その多くは対話の先で業務が止まっていることが原因です。
たとえば、
- 問い合わせ内容は聞き取れたが、システム処理につながらない
- 条件分岐が複雑で、途中で人手対応に戻ってしまう
- 音声対応とテキスト対応が分断されている
といった状況では、対話型AIは「回答するだけの存在」になってしまいます。これでは、業務効率化やCX向上といった本来の目的を十分に達成できません。
組み合わせ前提で考える対話型AI設計
こうした課題を踏まえると、対話型AIは「用途ごとに使い分ける」のではなく、業務全体を前提に組み合わせて設計する発想が重要になります。
- 音声で受けた情報をテキストで整理する
- テキスト対話で補足確認を行い、業務処理につなげる
- AI同士が役割分担し、人手対応を最小限にする
このように、対話型AIを単体ツールとしてではなく、業務を進めるための仕組みの一部として設計することが、導入効果を高めるポイントになります。
対話型AIを業務につなげるために重要なこと
対話型AIは、単に人と会話を行う技術ではなく、業務の入口として人とシステムをつなぐ役割を担う存在です。テキスト対話型AIや音声対話型AIにはそれぞれ強みがありますが、どれか一つを導入すれば業務が完結するわけではありません。
本記事で整理してきたように、対話型AIを業務で活用するためには、次の視点が重要です。
- 対話型AIをツールではなく、業務の流れの一部として捉える
- 業務を対話・判断・処理に分解し、役割を整理する
- 対話の先で業務が止まらない設計を意識する
特に音声対応を含む業務では、聞き取りや分岐の難しさから、対話型AI単体では対応しきれないケースも少なくありません。そのため、音声対話を起点にしながら、テキスト処理や業務ロジックと連携させる考え方が現実的になります。
こうした設計思想に基づくアプローチの一例が、CAT.AI マルチAIエージェント for Voice です。音声による対話を入口に、複数のAIが役割分担することで、従来のボイスボットでは難しかった業務対応までつなげることを想定しています。
対話型AIの導入や見直しを検討している方は、具体的な業務設計の考え方や活用イメージを、CAT.AI事例集を通じて確認いただけます。自社業務に当てはめながら検討を進める際の参考になります。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。

.jpeg)