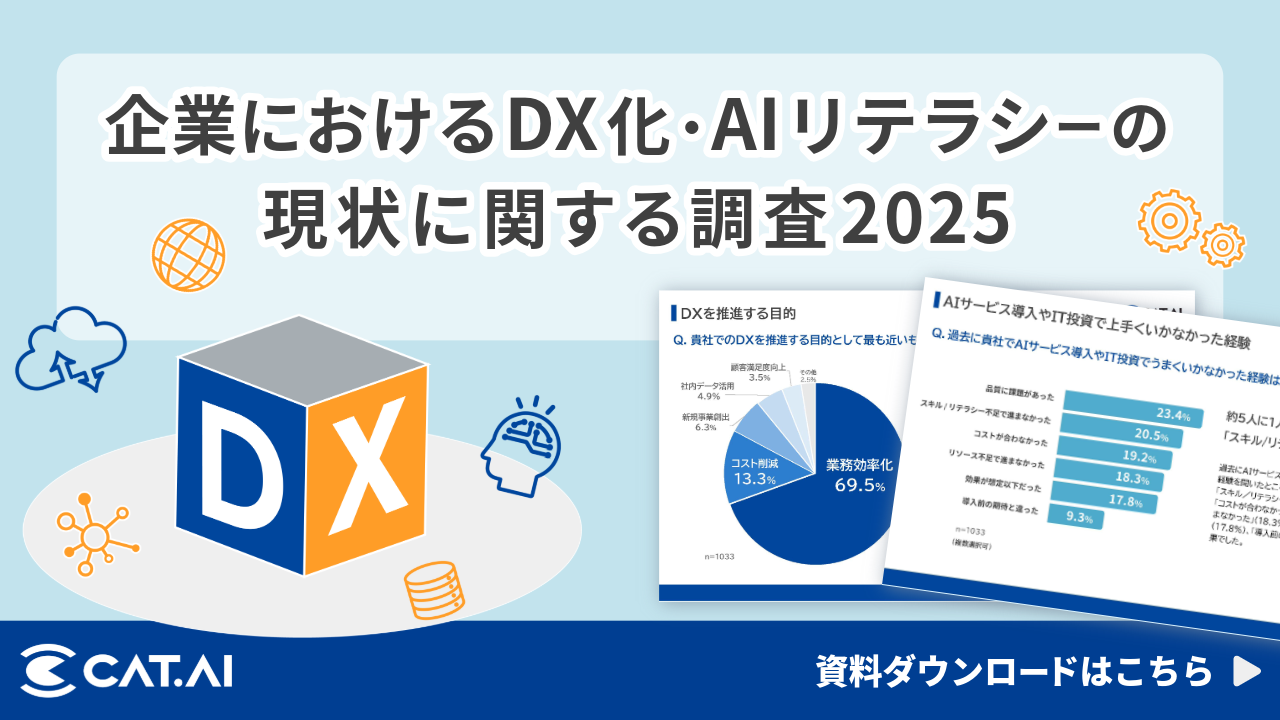マルチAIエージェントとは?仕組みと導入メリットを徹底解説

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が新たな段階に入る中、個別業務の自動化から、部門をまたいだ全体最適化へと企業ニーズが変化し、マルチAIエージェントが重要な要素として注目を集めています。
生成AIの進化に伴い、複数のAIが連携して複雑な業務を自動化するこの新しい技術は、DX推進の切り札となり得る存在です。本記事では、マルチAIエージェントの基本的な仕組みから、従来のRPAやチャットボットとの違い、具体的な活用事例までを分かりやすく解説します。
従来の自動化ツールでは難しかった“部門横断的な業務自動化”を、マルチAIエージェントがどう実現するのかを具体的に見ていきましょう。
Index
マルチAIエージェントとは?注目される背景
マルチAIエージェントは、従来の自動化ツールでは対応が難しかった、条件に応じた処理や連携が必要な複雑な業務を自動化する次世代の仕組みです。複数のAIが連携し動くことで、一気通貫で業務の完結を目指します。
マルチAIエージェントの定義
マルチAIエージェントとは、与えられた指示や目標に基づき、複数の専門的なAIエージェントが連携し、複雑なタスクや目標を達成するシステムのことです。
単一のAIが特定の作業を行うのに対し、まるで一つの組織のように役割を分担し、情報収集、分析、条件に応じた処理、実行といった多段階の業務フローを途切れなく自動化できるのが特徴です。
なぜ今、マルチAIエージェントが注目されるのか?
マルチAIエージェントが、業務自動化を牽引する仕組みとして注目される背景には、主に以下の3つの要因があります。
生成AIと大規模言語モデル(LLM)の進化
生成AIは、文章作成や情報整理などのタスクをAI自身が行える能力を指します。その中でも大規模言語モデル(LLM)は、膨大な情報から文脈を理解し、適切な情報抽出や要約ができる点が特徴です。
これらの技術の進化により、従来は人手に頼っていた情報整理や初期分析の部分はAIが効率的に支援できるようになりました。ただし、複数工程にまたがる業務や部門横断的なタスクを「統合して自動化」するには、単体の生成AIやLLMだけでは不十分なため、そういったことが実現できるマルチAIエージェントへの注目が高まっています。
従来ツールの限界(RPAや単一機能AI)
これまでのRPAや、特定の機能に特化した単一AIだけでは、例外処理が多い非定型業務(例:顧客からの個別問い合わせ対応や契約書レビュー)や、複数のシステム・部門をまたぐ業務フロー(例:受注から請求、カスタマーサポートまでを跨ぐ処理)に対応しきれないケースが増えています。
DX推進と高度な自動化へのニーズ
人手不足が進む中、従来の手作業や単機能ツールでは、部門間やシステム間で業務が分断され、人との連携が不可欠な工程が多く残っています。そのため、業務効率の改善やサービス品質向上において根本的な対策になりきれないケースが少なくありません。
また、企業間競争が激化する状況では、迅速かつ正確に業務を遂行する能力が差別化のポイントとなります。こうした背景から、複数工程や部門をまたぐ業務も含め、高度な自動化による業務統合・効率化のニーズが高まっています。
マルチAIエージェントの主な機能と構成要素
マルチAIエージェントは、司令塔役の「リードエージェント」、実務を担う「専門エージェント」、そして外部システムと接続する「ツール連携」という3つの要素で構成されています。
これらがどのように連携して一つの目標を達成するのか、その全体像と各要素の役割を見ていきましょう。
リードエージェント:全体の司令塔
ユーザーの指示を受け、目標達成のための計画を立案します。各タスクを最適な専門エージェントに割り振り、進捗を管理して成果物をまとめます。
専門エージェント:各分野のスペシャリスト
特定のスキルに特化したAIで、リードエージェントの指示に従いタスクを実行します。
例:
- 情報収集エージェント:Webや社内データからの情報抽出
- データ分析エージェント:収集データの統計分析・傾向分析
- アウトプットエージェント:分析結果の資料作成・要約生成
必要に応じて専門エージェント同士がデータをやり取りしながら、タスクを遂行します。
ツール連携:外部システムとの連携機能
専門エージェントは外部ツールと接続することで実務を実行します。
- Web検索や外部データベースへのアクセス
- 社内CRM・ERPなどのシステム参照やデータ登録
この仕組みにより、AIは分析だけでなく、実際の業務アクションまで対応可能です。
マルチAIエージェントが動く仕組み
ユーザーからの指示が、AIチームによってどのように処理され、業務が完結するのか、一連の流れをステップで解説します 。
- タスク分解(司令塔AI)
リードエージェント(司令塔AI)が目標を理解し、達成に必要な具体的タスク(情報収集、データ分析、レポート作成など)に分解します。 - 役割分担(司令塔AI → 専門AI)
リードエージェントが、分解されたタスクを最も得意とする専門エージェントに割り振ります。 - タスク実行・連携(専門AI同士)
各専門エージェントがそれぞれのタスクを実行し、必要に応じてデータや途中経過を共有しながら連携して業務を進めます。 - 成果物の生成
すべてのタスクが完了した後、最終的な成果物(レポートや顧客への回答など)をユーザーに提供します。
チャットボット・RPA・単一のAIエージェントとの違いは?
マルチAIエージェントの仕組みや特性は、従来の自動化ツールと比べると理解しやすくなります。
チャットボットとの違い:対話から業務実行までの「完結力」
- チャットボット
あらかじめ設定されたシナリオやFAQに基づく応答が得意なチャットボットは、一問一答など、定型的な問い合わせ対応に強みがあります。 - マルチAIエージェント
対話内容に応じて、データ取得や資料作成、関連業務の実行までを自動で処理することが可能です。単なる質疑応答ではなく、業務の一連の流れを対話から一気通貫で完結できます。
RPAとの違い:状況に応じた非定型業務への「柔軟な対応力」
- RPA
決まった手順やルールに沿って繰り返し作業を自動化するのに適しているRPAは、定型業務の効率化に貢献します。 - マルチAIエージェント
状況に応じて複数のAIが情報を分析し、状況に応じた処理を行いながら業務を進めることが可能です。例えば問い合わせ内容に応じてデータ検索や資料作成まで、決まった手順や、シナリオ通りではないケースや非定型の業務も自動化できる点がRPAとの違いです。
単一のAIエージェントとの違い:複数タスクを統合処理する「連携力」
- 単一のAI
特定のタスクに特化しているため、業務が「情報収集」「分析」「実行」といった個別タスクで分断されやすくなります。 - マルチAIエージェント
複数のAIが役割を分担しながら協調して動くことで、分断されていた業務フロー全体を統合的に進められます。これにより、部門横断的で多段階の複雑な業務も効率的に処理できます。
【業界・業務別】マルチAIエージェントの具体的な活用事例

マルチAIエージェントを導入することで、具体的にどのような業務が可能になるのか、3つの業界での活用事例をご紹介します
活用事例1:コンタクトセンターでの顧客対応自動化
顧客からの「キャンペーン対象か確認し、対象なら特典と手続き方法を教えてほしい」という問い合わせに対し、以下のように動作します。
- リードエージェントがタスクを分解(対象者確認、特典内容提示、手続き案内)。
- オペレーショナルAIが社内CRMにアクセスし、顧客IDから対象条件を満たしているかを照会。
- 複数のAIが連携して、照会結果とキャンペーン情報を統合し、顧客に合わせたパーソナライズされた回答文を作成。
- ナビゲーションAIが回答文を顧客に提示し、必要に応じて次のアクション(申込ページへの誘導など)を案内。
活用事例2:マーケティング部門でのデータ収集・分析・レポート作成
「競合A社の新製品発表に関する市場の反応を分析し、レポートにまとめてほしい」という指示があったケースでは、マルチAIエージェントは以下のように動きます。
- リードエージェントがタスクを分解(Webリサーチ、SNSデータ収集、データ分析、レポート作成)。
- 複数のAIが連携して、Web検索ツールやSNS分析ツールと連携し、必要な情報を収集。
- 分析AIが収集した膨大なデータを分析し、市場の傾向、ポジティブ/ネガティブな反応を抽出。
- レポート作成AIが分析結果を基に、指定されたフォーマットで企画書やレポートを自動生成。
活用事例3:製造業でのサプライチェーン最適化
「次月の生産計画を、最新の需要予測と現在の在庫レベルに基づいて自動で最適化してほしい」という指示があった場合、マルチAIエージェントは以下のようなフローで動きます。
- リードエージェントがタスクを分解(市場データ収集、需要予測モデル実行、在庫データ照合、生産計画調整)。
- 分析AIが外部の市場データや販売実績データを取り込み、高度な需要予測モデルを実行。
- データ取得AIが社内ERPシステムから現在の在庫情報をリアルタイムで取得。
- すべての情報を統合したリードエージェントが、最適な生産計画案を立案し、担当者に承認を求める通知を自動送付。
マルチAIエージェント導入のメリットと注意点
マルチAIエージェントを導入する際には、その大きな利点だけでなく、特有の注意点も理解しておく必要があります。
導入によって得られる3つのメリット
従来のRPAや単一AIとは異なる、マルチAIエージェントならではの価値は以下の3点です。
非定型業務の自動化と業務完結率の向上
マルチAIエージェントでは、例外や判断を伴う非定型業務を、複数のAIが連携して順序立てて処理できます。これにより、業務の分断を防ぎ、AIによる業務完結率を飛躍的に高めます。まさにマルチAIの「連携力」が活きる部分です。
業務の標準化と属人化の解消
AIが連携して統一的なフローを実行することで、人的な判断ミスや経験依存を減らし、業務の質を安定化させます。複雑な知的労働を複数のAIが連携して担うことで、属人化を解消できます。
スケーラビリティの向上
タスクや業務量の増減に応じて、AIエージェントを柔軟に追加・組み合わせできます。複数のAIが協力して動く前提のプラットフォームであるため、大規模な業務や変化の激しい状況にも対応しやすいです。
導入前に知っておきたい注意点と対策
マルチAIエージェントの導入前に検討すべき注意点と対策を解説します。
複雑なタスク連携による障害リスク
複数のAIが依存関係を持って動作するため、一部のAIの処理遅延やエラーが全体のフローに影響を及ぼす可能性があります。
対策: タスクの依存関係を可視化・監視できる管理ツールを導入し、障害発生時に影響範囲を特定し、部分的にリカバリーできる仕組みを整えることが重要です。
AI判断プロセスのブラックボックス化
専門AI同士が連携して処理が進められるため、最終的なアウトプットに対し「どのAIが、どの情報に基づいて、どう判断したか」が不明瞭になりやすい側面があります。
対策: AIの意思決定プロセスや参照したデータソースの履歴をログとして記録・可視化できるソリューションを選定し、運用者が後から判断根拠を追跡できる仕組みがあると良いでしょう。
セキュリティとガバナンスの複雑化
複数のAIが社内外の様々なシステムにアクセスする場合、AIごとの権限管理や、システムを横断したデータ取り扱いルールの統一が必要となり、ガバナンスが複雑化します。
対策: 各AIエージェントのアクセス権限を明確に定義し、オンプレミス環境やプライベートクラウドでのデータ分離、監査ログの管理を徹底するなど、厳格なセキュリティポリシーを設計・適用することが重要です。
複雑な業務フローも自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」
企業の現場では、部門を横断する非定型業務や、判断・分析を伴う複雑なタスクが増えています。従来のRPAや単一のAIツールでは、こうした業務を一気通貫で自動化することが難しく、部分的な自動化に留まるケースが多く見られました。
このような課題を解決するのが、複数の専門AIが連携して動作する「マルチAIエージェント」です。各AIが役割を分担し、情報収集・分析・判断・実行までを統合的に処理することで、これまで手作業や複数のツールに分断されていた業務フローを効率的に完結させることができます。
こまで紹介したマルチAIエージェントの考え方は、あくまで仕組みや概念の説明です。
実際にこの構造を現場で機能させるには、複数AIの連携を最適に制御できるプラットフォームが必要になります。この仕組みを具体的に実装したソリューションとして、当社が提供する 「CAT.AI マルチAIエージェント」 をご紹介します。
このプラットフォームでは、司令塔となるリードエージェントの指示のもと、
Navigational AI: ユーザーとの対話を円滑に進めるナビゲーター担当
Generative AI: 高度な思考や分析、文章生成を担うアウトプット担当
Operational AI: 外部システム連携や定型作業を実行するタスク実行担当
といった複数の専門エージェントが連携し、部門をまたぐような複雑な業務フローを自動化します。
従来のツールでは対応が難しかった業務の一連の流れをAIが「完結」させることで、企業のDX推進を強力にサポートします。
マルチAIエージェント導入を成功させるためのポイント
マルチAIエージェントの導入効果を最大化するためには、戦略的なアプローチが求められます。ここでは、成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。
ポイント1:導入目的と運用ルールを明確化する
まず、「AI導入」そのものが目的化しないよう、戦略の根幹を固めることが重要です。
- マルチAIエージェントならではの価値を明確にする
単一AIでは難しい部門横断の業務自動化や複雑なプロセスの支援など、マルチAIエージェントを活用して実現したい具体的な価値を明確化します。その上で、「レポート作成時間を50%削減する」「問い合わせの一次完結率を85%にする」といった具体的な数値目標を設定しましょう。 - 組織横断の運用ルールを策定する
複数のAIが部門をまたいで動作する場合、各部門の業務ルールや優先順位をAIに統合する必要があります。トラブル時の対応フローや優先度の決め方など、運用ルールを明確にしておくことがスムーズな運用の鍵となります。
ポイント2:AI間の連携と判断プロセスを設計する
マルチAIエージェントでは、AI同士の連携が成果に大きく影響します。そのため、設計段階でデータや処理フローを丁寧に整えることが重要です。
- データとAI間の連携・判断プロセスを設計する
AI同士が効率的に動くには、データ形式や受け渡しタイミングを統一することが重要です。どのデータを、どの形式で、いつ渡すかを事前に明確化します。 - AI判断の可視化・モニタリング体制を整える
複数AIの連携により、アウトプットに至る過程が見えにくくなることがあります。各AIの処理ログや参照データを追跡可能にし、運用状況をモニタリングできる体制を整えます。
ポイント3:スモールスタートで段階的に展開する
最初から大規模な導入を目指すのではなく、リスクを抑え、着実に成果を出すための段階的なアプローチを推奨します。
- 小規模なフローで効果を検証する
まず特定業務や部門に限定して試行します。タスク分解やAI間の連携が計画通りに機能するか確認し、段階的に改善します。 - 現場部門を巻き込みながら改善を続ける
AIと協働するのは現場部門です。導入初期から現場の意見を取り入れ、小さな成功体験を積み重ねることで、実用的で業務に役立つシステムに成長させます。
マルチAIエージェントで次世代の業務自動化を実現
本記事では、マルチAIエージェントの基本的な仕組みから、具体的な活用事例、導入を成功させるためのポイントまでを解説しました。
マルチAIエージェントは、単なる業務効率化ツールではありません。複数のAIエージェントが互いに連携し、データ分析や複数工程を伴う顧客対応業務など、これまで人間にしかできなかった複雑な知的労働を自動化することで、企業の生産性を高め、新たな価値を創造する可能性を秘めた革新的なテクノロジーです。
単一ツールでは分断される業務も、統合的に自動化できるため、より高度な業務自動化を目指す企業にとって、マルチAIエージェントはDXを加速させる強力なエンジンとなるでしょう。
さらに理解を深めたい方は、CAT.AI マルチAIエージェントの詳細な機能や利用シーンをまとめた資料をご活用ください。複雑な業務の自動化方法や運用のポイントを具体的に確認でき、実務への応用を検討する際に役立ちます。
また、国内企業のDXやAI活用の現状をまとめた調査レポートもあわせてご活用ください。自社の立ち位置を客観的に把握でき、導入検討や今後の戦略立案に役立ちます。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。