AI型チャットボットでEFO(入力フォーム最適化)を達成させる!コンバージョン率改善のための導入方法
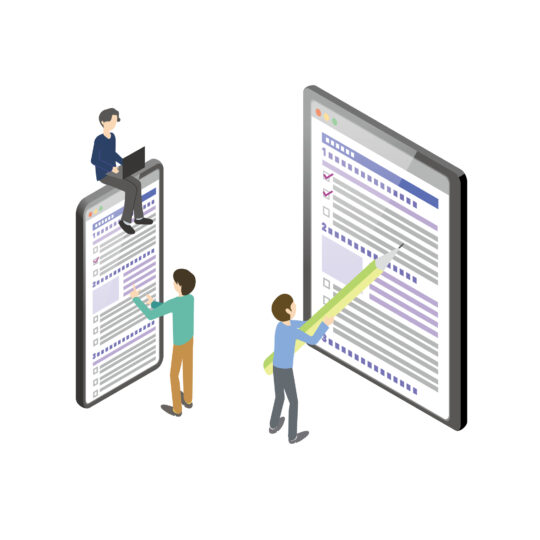
Webサイトからのコンバージョン率を改善させるためには、申し込みや購入時に必ず通る「入力フォーム」をユーザーがストレスなく入力出来るものにすることが重要です。
入力フォームを改善するにあたっては、EFOツール(入力フォームを最適化する専用ツール)の導入を検討する方が多いと思います。しかし、「EFOツールの代わりにAI型チャットボットを活用する」という方法もあることをご存知でしょうか。
AI型チャットボットをEFOに活用することで、「入力フォームへ誘導しやすくなる」「チャット形式で入力のハードルを下げる」など、EFOツールとは違ったメリットがあります。
今回の記事では、EFOツールとAI型チャットボットの違いをお伝えしながら、AI型チャットボットでEFOを達成しコンバージョン率を改善するための方法について分かりやすく解説します。
Index
EFOとは?
EFOとは、Entry Form Optimizationの頭文字をとったものです。直訳すると「入力フォーム最適化」となり、主にビジネスでは「入力フォームの離脱率を改善するための施策」を指します。
ユーザーがストレスなく入力できるようにフォームを改善することによって、入力完了率を向上させ、コンバージョン率を改善させるための施策です。
Webサイトでは資料請求や問い合わせ、会員登録、申し込み、購入など多くの場面で入力フォームが使われているため、ユーザーの離脱率が高い入力フォームはコンバージョン率の低下に直結します。
離脱率の高い入力フォームの例
ユーザーの離脱率が高い入力フォームとはどのようなものでしょうか。以下はユーザーが離脱しやすい入力フォームの代表的な例です。
- 入力する項目が多い
- 頻繁にバナーやリンクが表示される
- エラー発生率が高い
- スマートフォンに最適化していない
それぞれ詳しくご説明します。
入力する項目が多い
「入力する項目が多い」のは、ユーザーが最も途中離脱しやすい例の一つです。ユーザーは入力する項目が多ければ多いほど、途中離脱しやすい傾向にあります。特に、「1画面あたりの項目数が多い」「複数ページに渡っている」などの場合は、ユーザーが負担を感じやすく、離脱に繋がる可能性が高いと考えられます。
頻繁にバナーやリンクが表示される
入力フォームの途中に関係のないバナーやリンクが表示される場合も、ユーザーの途中離脱に繋がる場合があります。入力途中に誤ってバナーやリンクをクリックしてしまうと、元のページに戻った時に入力した内容がリセットされてしまうことがあります。そうなった場合、多くのユーザーは入力を諦めてしてしまうでしょう。
エラー発生率が高い
入力フォームではエラーが発生することがありますが、Webサイトの設計がしっかりとされていない場合にはエラー発生率が高くなってしまいます。エラー発生率が高いサイトはユーザーにストレスを与え、さらに入力した情報がリセットされてしまった場合には、ユーザーが途中離脱する可能性は高くなります。
スマートフォンに最適化していない
入力フォームをパソコン用の画面表示にのみ最適化している場合、スマートフォンで表示した際に文字サイズやレイアウトが最適化せず、閲覧や入力がしにくくなってしまいます。モバイル端末が一般的となっている現代では、ページビューの7〜8割がスマートフォンで閲覧されていると言われていることからも、スマートフォンに最適化していない入力フォームでは途中離脱が増えてしまうでしょう。
以上の項目に共通することは「ユーザーにとって使いにくい」ということです。もし自社サイトの入力フォームが上記に当てはまる場合は早急なEFOが必要です。
EFOツールについて
EFOを行うにあたっては、EFO専用である「EFOツール」というものがあり、ツールによって付属機能も異なります。
以下はEFOツールに備わっている代表的な機能です。
| カラーリング | 必須項目を色付けでハイライト |
| 住所自動入力 | 郵便番号を入力すると住所を自動入力 |
| キーボード最適化 | 入力項目によって「カナ」や「英数字」などを自動で切り替え |
| リアルタイムエラー | 送信ボタンを押す前にエラー部分を表示 |
EFOツールは、入力フォームに辿り着いたユーザーがスムーズに入力を完了できるようにサポートを行うツールといえます。
AI型チャットボットとは
AI型チャットボットとは、人工知能が搭載されたチャットボットを意味します。チャットボットはchat(会話)とrobot(ロボット)が語源になった言葉で、AI(人工知能)が搭載されたチャットボットでは、AIがよくある質問と答えを学習しユーザーの疑問に柔軟に回答することが出来ます。
【関連記事】AIチャットボットとは?基本的な仕組みと活用がおすすめのシーン
チャットボットには、フローチャート形式のシナリオ設計に基づいてユーザーに回答する「シナリオ型チャットボット」もありますが、EFOツールとしてチャットボットを導入する場面ではAI型チャットボットがおすすめです。
これは、AI型チャットボットが「フリーワードでやり取りができる」ということが大きな理由です。AI型チャットボットはWebサイトの画面上に表示しておくことでユーザーの質問に答えるなど、入力フォーム以外の場面でもコンバージョンに繋がるサポートをすることが出来ます。
このように、AI型チャットボットをEFOツールとして導入した場合、EFOツールには無い「AI型チャットボットならではのメリット」も存在します。
EFOにAI型チャットボットを活用するメリット

EFOツールが「入力フォームに辿り着いたユーザーのサポートを行うこと」に対し、AI型チャットボットの場合は「常に申し込みを受けられる環境を構築できる」「コンバージョンに繋げるためのサポートが出来る」「入力におけるユーザーの心理的負担をより少なく出来る」などのメリットがあります。
主な理由は以下の通りです。
- 入力フォームを探す必要がない
- ユーザーの質問に答えられる
- チャット形式で利用出来る
- ページ遷移の必要がない
- Webサイト全体の分析が出来る
それぞれ詳しくご紹介します。
入力フォームを探す必要がない
AI型チャットボットはWebサイトの画面上に常に表示させておくことができるため、ユーザーは入力フォームを探さずともチャットボット経由ですぐに購入や申し込みを行えるようになります。
例えば、AI型チャットボットに「サービスの申し込みをしたい」「会員登録をしたい」などと入力するだけで、そのままユーザーをゴールまで誘導していくことが可能です。これにより、入力フォームを探すというアクションを減らすことや、問い合わせ方法を見つけられずに離脱してしまうユーザーを減らすことが出来ます。
ユーザーの質問に答えられる
AI型チャットボットはユーザーのフリーワードでの質問に答えることが出来るため、申し込みや購入にあたっての疑問や不安を解消し、コンバージョン獲得に繋げることができます。
Web上においてユーザーが疑問や不安を持った場合、そのまま離脱してしまうことも少なくありません。AI型チャットボットで即座に質問できる環境を作ることで、「調べてまた今度にしよう」というユーザーを減らすことに繋がります。
入力フォームに辿り着く前からコンバージョンに向けてのサポートが出来る点は、AI型チャットボットの大きなメリットと言えます。
チャット形式で利用できる
AI型チャットボットはチャット形式でやりとりを行うため、より気軽に利用することが出来ます。
ユーザーは質問に対して回答を入力することを繰り返し、会話をするように必要項目の入力が進んでいきます。一画面に多くの項目が並んでいるよりも心理的負担は少なくなり、完了率も高まると考えられます。
さらに、入力途中に分からない事があればAIに質問しながら進められるため、途中離脱することなくユーザーに入力を完了してもらいやすくなります。
ただし、これは搭載されているAIの精度によって異なるため、ツール選定時にはAIの精度につい一ても確認するようにしましょう。
ページ遷移の必要がない
AI型チャットボットとのやりとりを通じて入力を進めていく場合、基本的にはページを遷移する必要がないため、読み込みエラーやブラウザバックでのリセット、操作ミスなどが避けられます。
これにより、ユーザーの大きなストレスの一因でもある「エラーの発生」や「入力がリセットされてしまった」などが原因での途中離脱を減らすことが出来ます。
Webサイト全体の分析が出来る
EFOツールにも分析・レポート機能は備わっているものはありますが、EFOツールにおける分析対象は基本的には入力フォームにおけるユーザーの動向が対象となります。
AI型チャットボットは入力時のユーザー動向はもちろん、Webサイト全体におけるユーザー動向を分析できる製品もあります。これにより、サービスをより良くするための改善に役立てることも出来るため、よりコンバージョン率改善に役立つと考えられます。
コンバージョン率改善のためのAI型チャットボットの導入方法

ここでは、コンバージョン率改善のためのAI型チャットボットの導入方法について解説します。AI型チャットボットの導入効果を最大限発揮するために非常に重要となりますので、以下の手順を十分に理解しておくようにしてください。
- Webサイトの課題を明確にする
- ツールを選定する
- AIにデータを学習させる
- UI設計を行う
- テスト運用を行う
- 運用後も定期的な改善を行う
1.Webサイトの課題を明確にする
Webサイトからのコンバージョン率改善にあたっては、入力フォームだけではなく、Webサイト全体の課題を明確にしてみましょう。「入力フォームだけの問題なのか」「見にくいサイトになっていないか」「どのような問い合わせが多いのか」など、まずはAI型チャットボットの導入によって課題が解決されるのかを検討するようにしてください。
2.ツールを選定する
自社が求める機能の有無やAIの精度について確認するようにしましょう。ここで言うAIの精度とは「自然言語処理」を意味します。AIが質問内容を判別したり回答を提示したりする際には、自然言語処理という技術が活用されており、この技術の精度が高いほど正確に質問を認識することが可能です。
ツールによって特徴が大きくことなりますので、必要なものが備わっているかを導入前に整理しておきましょう。
3.AIにデータを学習させる
AIが対応するにあたって必要なデータを学習させていきます。入力フォームに関わる内容はもちろん、よくある質問なども学習させることでユーザーの質問に対応することが出来ます。精度の高いデータが多いほどAIの対応精度も高くなるため、あらかじめ多くのデータを用意しておくと効率的です。
4.UI設計を行う
チャットボットにおけるUI設計とは、見た目のデザインや文章構成などの設計を指します。目に留まりやすいデザインや文字の大きさ、簡潔な文章などユーザーが使いやすい・使いたくなる設計を意識していくことが大切です
5.テスト運用を行う
全ての準備が整ったら、テスト運用を行います。より多くのユーザーに利用してもらうために、使い方の例やポイントなどを提示すると利用率が高くなる傾向にあります。
6.運用後も定期的な改善を行う
テスト運用に問題がなければ、運用を開始します。ただし運用を開始したら終わりではなく、定期的に分析しレポート内容を参考に改善を繰り返していくことでコンバージョン率の改善に効果を発揮しやすくなります。
AI型チャットボットでコンバージョン率を改善しよう!
EFOツールとしてAI型チャットボットを導入することで、「Webサイトの画面上に常に入力フォームがある環境を構築できる」「入力フォームよりも気軽に利用できる」「ユーザーの疑問や不安をその場で解消出来る」などコンバージョンに繋がる多くのメリットがあります。
Webサイトからのコンバージョン率の改善を考えていらっしゃる方は、EFOツールとしてAI型チャットボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
トゥモロー・ネットが提供するCAT.AI GEN-Botは、生成AIと連携し企業が保有するあらゆるデータベースに基づいてテキストだけではなく、画像やフォームも使いながら適切な回答を作成・提示し、パーソナライズした対応で問題解決に導くことができるシステムです。
高度なデータベースとBot機能でオープンデータ使用を制御し、生成AIの課題でもあるハルシネーションの発生を最低限に留め適切な回答を提供することに加え、独自開発のNLP(自然言語処理)エンジンを搭載し、データ検索の精度を向上します。
企業の公式サイトやアプリ、チャットでの問い合わせ・FAQなどのフロントチャネルとしての活用に加え、社内規定やガイドライン、専門職のナレッジ統合ツールなどの従業員サポート・社内ヘルプデスクとして利用することができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。


.jpeg)




