AIチャットボットの運用は内製化できる?メリット・デメリットと成功のポイントを解説
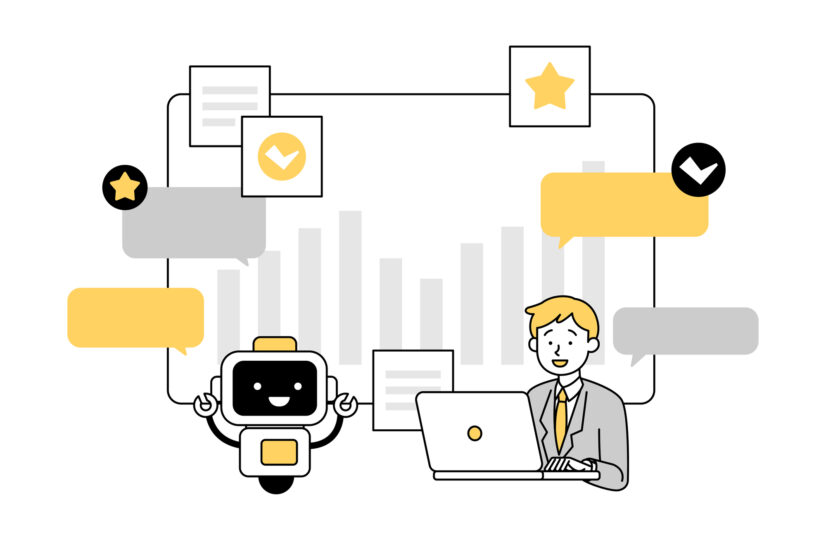
顧客対応や問い合わせ業務の効率化を目指し、多くの企業がAIチャットボットを導入しています。しかし、導入後の運用では「どのくらい社内で対応できるか」「外部委託に頼るべきか」といった悩みが浮かび上がることも少なくありません。
AIチャットボットは、導入しただけでは十分な効果を発揮できず、ログ分析や回答精度向上のためのチューニング、追加データの学習など、継続的な運用が必要です。
本記事では、AIチャットボット運用を内製化するメリット・デメリット、必要な人材、運用成功のポイントを整理します。さらに、内製化の負荷を軽減しつつ高度な自動化も可能な「マルチAIエージェント」についても解説します。この記事を読むことで、自社で運用体制を構築する際の課題やポイントが明確になり、効率的な運用の方向性をイメージできます。
Index
AIチャットボットの運用を内製化するメリット
自社の業務や顧客特性に合わせ、改善サイクルを迅速に回せる点が大きな特徴です。運用状況やユーザーの反応を直接把握できるため、改善の優先度を柔軟に判断でき、担当者間でノウハウを蓄積することも可能になります。また、社内の知見として定着することで、将来的なAI導入や他システムとの連携に活かすことができ、長期的な運用効率の向上にもつながります。
内製化には具体的に以下のようなメリットがあります。
- スピーディーに対応できる
社内で運用することで、新サービスリリースやFAQ変更時などに即座に更新や学習が可能です。外部委託のようにタイムラグが生じることもありません。 - コストを抑えられる
外部委託のランニングコストが不要になり、社内に知見があれば分析・改善作業を低コストで実施できます。 - セキュリティリスクを軽減できる
顧客情報や社内データを自社環境で管理可能。外部クラウドに預ける場合に比べ、情報漏洩リスクを低減できます。
AIチャットボット内製化で直面する課題
AIチャットボットを社内で運用する場合、メリットがある一方で、運用負荷や体制面での課題も意識する必要があります。特に、作業量の多さや専門知識の必要性を過小評価すると、担当者の負担が増大したり、改善サイクルが滞ったりすることがあります。このような背景を理解した上で、内製化に取り組むことが重要です。
具体的には以下のような課題があります。
- 人的リソースの確保が必要
ログ分析、チューニング、データ学習、改善施策の立案など、多くの作業が発生します。 - 担当者の負担が大きくなる
他業務と並行して運用を行う場合、作業が継続できず負担が集中するリスクがあります。 - 運用・管理がおろそかになるケースがある
継続的なメンテナンスができないと回答精度が低下し、利用されなくなる可能性があります。
AIチャットボット内製化に必要な人材とスキル
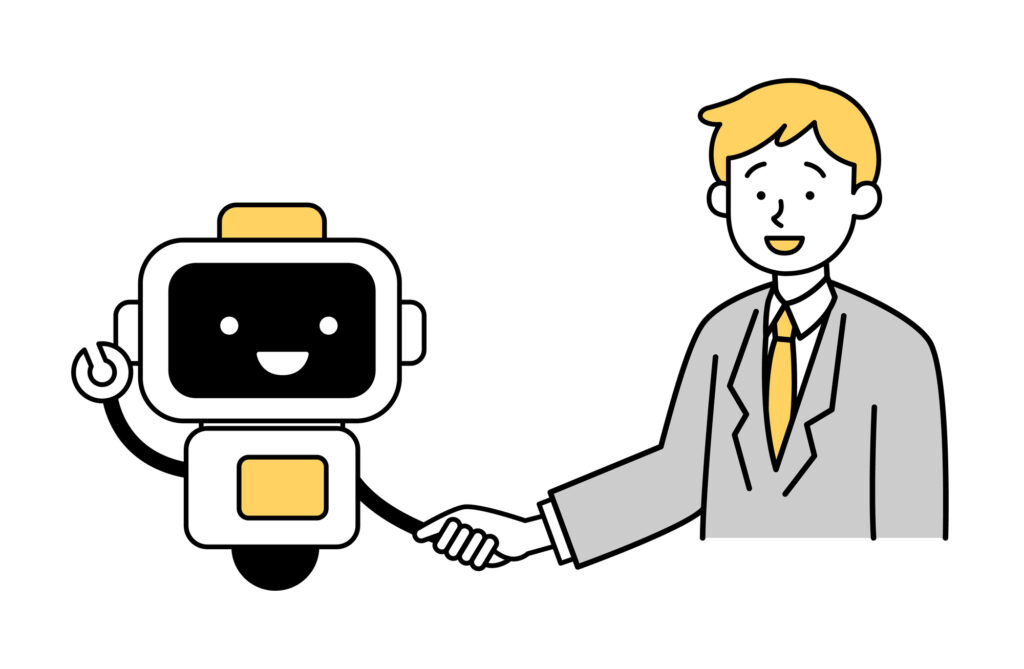
AIチャットボットを効果的に運用するためには、単にツールを操作できるだけでは不十分です。運用担当者は、システムの挙動やユーザーの反応を理解し、改善策を自律的に考え、実行できることが求められます。そのため、内製化には以下のようなスキルや能力を持つ人材が必要です。
- AIに関する知識とスキル
自然言語処理や機械学習など、チャットボット運用に不可欠な技術を理解していること。 - 問題解決能力
利用率の低下や回答精度不足といった課題を分析し、改善策を考え、実行できる力。
社内に十分な人材がいない場合でも、外部講師による研修や社内講習制度、資格取得支援などで補うことが可能です。こうした取り組みを通じて、社内での運用体制を強化することができます。また、必要に応じて外部ベンダーに運用や改善の一部を委託することで、負担を軽減しつつ安定した運用を実現することもできます。
AIチャットボット内製化を成功させるポイント
AIチャットボットの内製化は、人材や技術の準備だけでなく、運用体制や作業フローを整えることも重要です。適切な運用体制が整っていないと、改善サイクルが滞ったり、担当者の負担が増大したりする可能性があります。そこで、内製化を効果的に進めるためには、以下のポイントを押さえることが有効です。
運用ルールや判断基準を社内標準化する
単なる「チーム運用」ではなく、質問分類や回答修正のルール、優先度判断の基準を明文化しておくことで、担当者間で属人化を防ぎつつ迅速に対応できます。例えばFAQの追加は「月2回、ユーザー問い合わせ件数と回答精度を基に優先度を決定」といった具体的なルールを設定すると効果的です。
改善サイクルをデータで可視化する
単に「メンテナンス日を設定」するだけでなく、ログ分析結果や応答精度、解決率をダッシュボードで可視化し、チーム全体で進捗や課題を共有します。数値で改善効果を追えることで、担当者間の議論が具体的になり、運用が回りやすくなります。
スモールスタート+段階的拡張
内製化をいきなり全業務で行うのではなく、まずは特定の問い合わせカテゴリや少数のFAQから始め、運用ノウハウを蓄積して段階的に範囲を広げます。これにより、担当者の負担を抑えつつ運用体制を安定化できます。
内製化と外部支援のハイブリッド活用
自社内で対応できる範囲と外部ベンダーに委託した方が効率的な範囲を明確に区分します。
例として、重要度の高い問い合わせは内製化し、一般的・定型的な問い合わせは外部ベンダーに対応してもらうと効率的です。
マルチAIエージェントで実現する効率的な内製化

従来のAIチャットボット(シングルAI)は、あらかじめ学習させたデータをもとにユーザーの質問に対応します。定型的な問い合わせには有効ですが、複雑な業務や幅広いデータ参照が必要な場合、対応が難しくなり、運用担当者には大きな負担がかかることがあります。
この課題を解決するのが、複数のAIエージェントが連携するマルチAIエージェントです。各AIが役割ごとにタスクを分担し、指令役のリードエージェントが全体を統括することで、従来のチャットボット運用で必要だった手作業の負荷を大幅に軽減できます。たとえば、問い合わせ内容の分類、関連情報の検索、回答文の生成といった処理をAI同士が連携して行うことで、担当者は個別のチューニングや細かい対応に割く時間を減らすことができます。
さらに、マルチAIエージェントは次のような特徴を持っています。
- 幅広いデータを参照できる:複数の社内データや外部データを横断的に活用し、複雑な問い合わせにも柔軟に対応できる。
- 継続的に改善できる:各AIが得た知見を統合し、全体の精度向上を自動化できる。
- 複数プロセスを自動化できる:単一タスクだけでなく、複数の業務プロセスをまたいだ対応をスピーディーかつ正確に実行できる。
このように、複数AIの分担によるマルチAIエージェントの活用は、従来のチャットボット運用では負担となっていた内製化の課題を解消し、より効率的な運用を可能にします。記事で紹介した内製化のポイントと併せて導入を検討することで、運用の負荷を抑えながら精度の高い顧客対応を実現できるでしょう。
マルチAIエージェントについては以下の記事で詳しく解説していますので、ご興味がある方はぜひこちらも併せてご覧ください。
内製化負荷を軽減しつつ効率的なAI活用へ
AIチャットボットの運用を内製化することで、スピーディーな対応やコスト削減、セキュリティリスクの軽減などのメリットが得られます。一方で、運用には専門知識や継続的なチューニング、改善策の実行が必要であり、担当者の負担が大きくなることも少なくありません。
こうした課題に対応する手段として、マルチAIエージェントの活用が有効です。
複数のAIが連携して業務を分担することで、従来は担当者が行っていた作業の多くを自動化でき、内製化の負荷を大幅に軽減できます。さらに、幅広いデータ参照や複雑なプロセスの自動化も可能になります。
当社で提供するCAT.AI マルチAIエージェント for Chatは、リードAIエージェントが司令塔となり複数のAIエージェントが連携してタスクを実行する仕組みを持っています。これにより、問い合わせ分類や情報検索、回答生成といった複数タスクを効率的に処理可能です。また、社内データやFAQ、外部情報など様々な情報を統合しながら回答を生成できるため、従来のシングルAIでは対応が難しかった複雑な問い合わせにも柔軟に対応できます。
このように、マルチAIエージェントを活用することで、内製化の負担を減らしつつ、高精度でスピーディーなAIによるチャット運用が可能になります。記事で紹介した内製化のポイントも踏まえ、マルチAIエージェントも選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。
詳細な説明や活用イメージは、CAT.AI マルチAIエージェントの製品資料でご確認ください。シングルAI(AIチャットボット)との違いや複数AIエージェント連携による自動化の仕組みを把握し、自社のDXやAI活用の検討に役立てることができます。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。



.jpeg)






