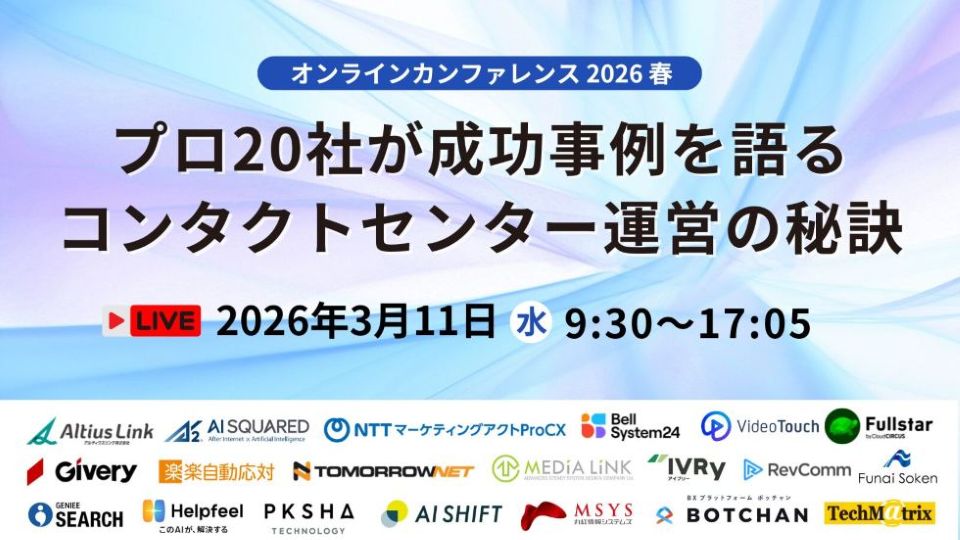AIボイスボットで進めるコールセンターDX~業務効率化とCX向上を両立する方法~

近年、コールセンターやヘルプデスクをはじめとしたカスタマーサポートの現場では、従来の人で対応する体制に限界が見え始めています。
人手不足、オペレーター教育の属人化、問い合わせ件数の増加、そして顧客の期待値の上昇ーこうした背景のなかで急速に注目を集めているのが、AIを活用した音声自動応答=ボイスボットの導入です。
AIによる電話対応の自動化は、業務効率化だけでなく、顧客満足度(CX)の向上やコールセンターDXの推進、さらには新たなビジネス価値の創出にもつながる、次世代型のソリューションとして脚光を浴びています。
当社が提供する「CAT.AI マルチAIエージェント for Voice」も、こうしたニーズに応えるソリューションの一つです。音声とテキストのマルチモーダルAI、LLMなど様々まAI技術を活用することで、従来の一次対応や簡易受付にとどまらず、柔軟なヒアリングや複雑な手続きにも対応可能です。また、CX視点に基づいたシナリオ設計と、導入後の効果を継続的に高める支援体制により、ボイスボット単体でも対応完了率を高める運用が可能となります。
本記事では、以下のような疑問に答えながら、企業がボイスボット導入を検討するうえで知っておくべきポイントを整理します。
- ボイスボットとは?
- 自社に導入するメリットとリスクは?
- 実際の導入パターンや事例にはどんなものがある?
- 導入を成功に導くために必要な視点とは?
最後には、本記事の内容をより深く解説しているホワイトペーパーをご案内します。社内検討を始めるご担当者様は、ぜひご活用ください。
CAT.AI マルチAIエージェント for Voiceはボイスボットをベースに、LLMやチャットボットが連携するコールセンターAIです。電話チャネルを自由にデザインしコールセターに新しいCX(顧客体験)を提供します。
Index
ボイスボットとは?
ボイスボットとは、AIを活用して音声による対話を自動化するシステムです。従来のIVR(プッシュボタン式の音声応答)とは異なり、自然言語処理によって、顧客の発話を理解・応答できるのが特長です。
ボイスボットは、電話対応業務の自動化を推進するうえで導入効果が高く、特に定型業務においては高精度かつ安定した対応が可能です。顧客にとっても操作ストレスが少ないため、UX・CXの向上に寄与するとして注目を集めています。
なぜ今、ボイスボットが注目されるのか?
企業の顧客接点の中でも、電話対応業務は依然として根強いチャネルです。特に、契約内容の確認、手続きの問い合わせ、緊急時の対応など、“今すぐ聞きたい”というニーズに応えるためには、電話というリアルタイム性が求められます。
しかし近年、この電話対応を取り巻く環境に大きな変化が起きています。主な変化は下記の通りです。
1. 人手不足とオペレーター業務負荷の限界
- コールセンター要員の確保が難しく、教育や定着率にも課題。
- ピークタイムの応答率低下、応対品質のばらつきが顕著に
2. 顧客接点の高度化と多様化
- 顧客は「すぐに」「簡単に」「正確な回答を得たい」と望むように
- 対応スピードと品質を両立するには、人手だけでは限界
3. DX推進とコスト最適化の必要性
- 「コールセンター自動化」は多くの企業のDXテーマに
- 可視化・データ活用・継続改善が求められる時代に
さらに、顧客の期待値も年々上がっており、「待たされた」「たらい回しにされた」「わかりにくい」といった体験は、企業イメージそのものに直結するようになっています。こうした背景のなかで、電話対応業務の一部または全部をAIで自動化できる「ボイスボット」が、解決策として注目されているのです。
活用パターン別に見る、ボイスボットの導入目的
ボイスボットは「とりあえず入れれば便利になる」ものではありません。
実際には、導入目的や業務の内容に応じて設計や活用方法が大きく変わるのが特徴です。
そのため、「どの業務で使うのか?」「何を自動化したいのか?」という視点を持って活用パターンを理解することが、導入成功への第一歩になります。
ここでは、よくあるボイスボットの活用パターンを3つに分類し、それぞれの特長と適した利用シーンを解説します。
1. 一次受付(FAQ対応)
- よくある問い合わせや営業時間案内などを即時自動応答
- 導入しやすい反面、対応範囲が限定されるためROIは低め
2. 簡易対応(事前ヒアリングなど)
- ユーザー情報の収集や用件の切り分けを自動で実施
- オペレーターへの引き継ぎ精度を高め、待ち時間短縮にも貢献
3. 複雑な定型対応(処理完結型)
- 住所変更や申込手続きなど、分岐の多い業務をAIで完結
- LLMとの連携により、ユーザーの幅広い意図を解釈しつつ柔軟で自然な対話を実現
- システム連携を前提に設計し、明確な業務削減とCX向上が実現
成功するボイスボット導入のカギは「設計と運用」にあり
ボイスボットはあくまで“仕組み”であり、その効果を最大限に引き出せるかどうかは設計と運用の質にかかっています。どの業務に適用するか、どうシナリオを構築するか、導入後にどのように改善を重ねていくか。導入前の戦略と、導入後の改善体制が両輪となってはじめて、ボイスボットは真の力を発揮します。
設計と運用のポイントは以下です。
自動化すべき業務の選定
「どの業務を自動化するか」は、ボイスボット導入成功の明暗を分ける最初の判断ポイントです。
コールセンターのすべての業務が自動化に適しているわけではありません。
実際には、問い合わせの種類・件数・対応時間・業務の複雑さなどを考慮しながら、優先順位をつけて自動化対象を見極める必要があります。
システム選定時のチェックポイント
「どの業務に使うか」が決まっても、「どのボイスボットを選ぶか」で成果は大きく変わります。市場にはさまざまなボイスボットソリューションがありますが、どの製品も同じというわけではありません。
特にエンタープライズ企業においては、拡張性・保守性・顧客体験(CX)・分析体制の4つの視点が、導入後の成功とROIに直結します。「まずは簡単なFAQ対応から…」というスモールスタートが多い一方で、将来的な拡張を想定しない選定は、やがて限界を迎え、再構築の手間とコストを招くこともあります。
“自動化”から“体験価値の革新”へ
これまでの観点をより体系的に整理し選定時にご参考にしていただけるよう、ホワイトペーパー『“とりあえず導入”は失敗の元 企業成長を支えるボイスボットの選び方とは?』で詳しく解説しております。
- ボイスボットのタイプ別比較と活用例
- 自動化すべき業務の見極めフレーム
- 導入成功のための設計・分析・運用ポイント
- 業界別の実践的なケーススタディ
など、社内の導入検討資料としてそのまま使える内容が詰まっています。
AIボイスボットは、ただの業務効率化ツールではありません。顧客との接点を“体験価値”に変えるテクノロジーです。
貴社のカスタマーサポートの未来を描く第一歩として、ぜひ本資料をご活用ください。
ボイスボットで自動化するべき業務の見極め方や、導入成功のための設計・分析・運用のポイントについてご紹介しています。
顧客体験を変革する CAT.AI マルチAIエージェント for Voice

ここまでご紹介してまいりましたが、AIによる業務自動化において、「顧客の体験」をどうデザインするかという視点は非常に重要なポイントとなります。
当社が提供するCAT.AI マルチAIエージェント for Voiceは、単に電話業務を自動化するツールではなく、音声とテキストを組み合わせたハイブリッド対応により、誰にとってもスムーズでストレスのない顧客体験を実現するソリューションです。また、LLMと連携することで、より自然で柔軟なAIによる対話を実現します。目的や業務内容に合わせ、様々なAIを最適に組み合わせながらAI対話をデザインします。
特に、“問い合わせに答える”のではなく、“課題を解決に導く”ためのシナリオ設計、そして導入後も成果を出し続けるための改善支援体制において高い評価を受けています。
もしご興味を持っていただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。




.jpeg)