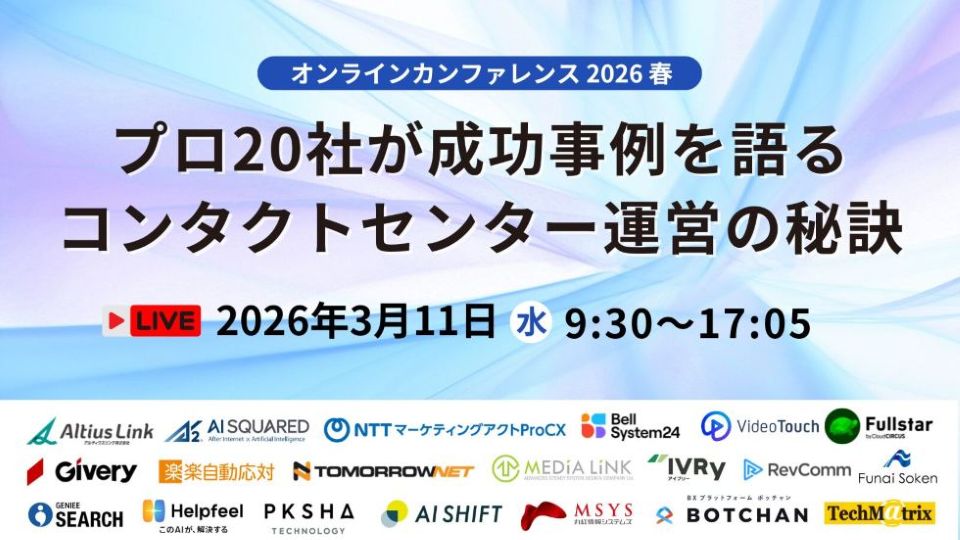AIオペレーターとは?仕組み・種類・導入メリットを業務別に解説

コールセンターやカスタマーサポート窓口では、対応の質と効率を両立させることが大きな課題となっています。
人手によるオペレーションでは、繁忙期の負荷や担当者による対応のばらつきが発生しやすく、対応の遅れや誤案内といったリスクも避けられません。さらに、オペレーターの採用や教育には時間とコストがかかり、繁忙期に合わせた柔軟な体制を整えるのも容易ではありません。
こうした状況を踏まえ、問い合わせ内容の整理や定型的な対応を自動化・補助することで、業務負荷を軽減し、対応品質を安定させる手段としてAIオペレーターが注目されています。近年では、AIの意図理解や表現力の向上により、より自然な対話や複雑な問い合わせの分類なども可能になりつつあり、単なる自動応答ツールを超えた価値を提供できるケースも増えています。
本記事では、AIオペレーターの仕組みや種類、導入時に押さえておきたいポイント、業務別の活用例までを整理します。自社の業務にどのような形でAIオペレーターを取り入れられるか、具体的なイメージを持ちやすくなります。
Index
AIオペレーターとは?いま企業で求められる背景
AIオペレーターとは、問い合わせ対応や業務受付などを担うAIの仕組みを指す言葉として使われることが多くなっています。電話やWEB・アプリなど様々なチャネルにおける複数の接点で活用されるケースもあり、人が行ってきた一次対応を分担する存在として位置づけられています。
従来の自動応答と比べると、あらかじめ設計されたルールや業務フローに沿って対話を進められる点が特徴で、問い合わせ内容の整理や案内業務を中心に活用が広がっています。
こうしたAIオペレーターが注目される背景には、顧客対応業務を取り巻く構造的な課題があります。
- 問い合わせ件数の増加と対応チャネルの多様化
Webやチャットが普及する一方で、電話対応も含めた複数チャネルを並行して運用する負荷が高まっています。 - 人材確保・育成の難しさ
オペレーターの採用や教育には時間がかかり、業務量の変動に柔軟に対応しづらい状況が続いています。 - 対応品質のばらつき
人による対応では、経験や知識の差がそのまま品質に影響することも少なくありません。
このような状況から、AIオペレーターは「人を置き換える存在」というより、対応業務を整理し、安定した運用を支える仕組みとして検討されるケースが増えています。
AIオペレーターでできること・できないこと
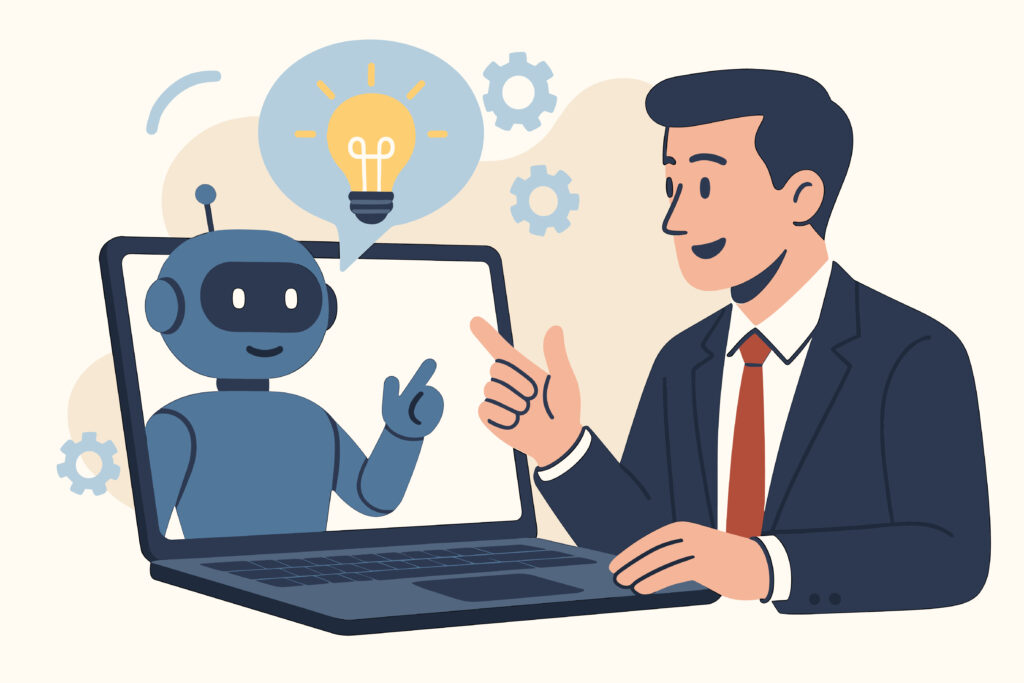
AIオペレーターの導入を検討する際は、AIが対応する範囲と、人の対応を前提とすべき範囲を整理しておくことが重要です。
この線引きが曖昧なまま進めてしまうと、過度な期待や運用上の混乱につながりやすくなります。
AIオペレーターが対応しやすいこと
・定型的な問い合わせへの一次対応
よくある質問や手続き案内など、内容が整理されている問い合わせは、AIによる対応が比較的安定しやすい領域です。近年は、生成AIの技術向上により、問い合わせの言い回しや意図の違いをある程度吸収し、文脈に沿った自然な案内を返せるケースも増えています。
・案内・誘導が中心の業務
担当窓口の案内や必要情報の提示など、一定の流れがある業務はAIオペレーターと相性がよいとされています。複数チャネル(Web、アプリ、電話など)にまたがる問い合わせにも、設計次第で統一的な案内が可能です。
・問い合わせ内容の分類・振り分け
用件を整理し、適切な担当や次の業務につなぐ役割として活用されます。曖昧な表現や複数の要素を含む問い合わせでも、一定レベルで意図を整理できるようになり、一次対応の負荷軽減や対応品質の安定化に寄与します。
人の対応が必要になりやすいこと
・感情的な配慮が求められる対応
クレームや個別事情が絡む相談では、状況に応じた判断や共感を含めた対応が求められます。AIが自然な応答を返せるようになっても、「どう対応するのが最適か」という判断そのものは、人が担う場面が多く残ります。
・例外処理が多い業務
ルール化しにくいケースが頻発する業務では、AIだけで完結させるのは難しいのが実情です。AIが判断材料を整理・提示することは可能でも、最終的な基準や例外の扱いは設計側・運用側で明確にする必要があります。
AIオペレーターの種類と設計の考え方
AIオペレーターは、その構成や役割によって大きく2つの考え方に分けて整理できます。
成果を左右するのは、どの業務をどこまで担わせるかという設計の視点です。
単体AIオペレーター型
- 対話エンジンとシナリオ応答が中心
あらかじめ用意した質問と回答を軸に、問い合わせ対応を進める構成です。 - スモールスタートしやすい
限定的な業務や、特定の問い合わせ対応から始めやすい点が特徴です。一方で、対応範囲を広げすぎると、シナリオ外の問い合わせが増え、結果として人への引き継ぎや対応の滞留が発生しやすくなる点には注意が必要です。
業務プロセスと連携するAIオペレーター
- 基幹システムやCRMと接続
既存システムと連携することで、受付内容をそのまま業務処理につなげる設計が可能です。応答だけでなく次の処理ステップへの案内やデータ更新も行えます。 - 対応完了までをサポート
問い合わせ応答の一連の流れを支える構成で、業務の効率化や負荷軽減に寄与します。
より複雑な判断や分散したタスクをスムーズに行う場合には、複数のAIが連携して動く仕組みと組み合わせて活用されることもあります。
AIオペレーターの主な活用シーン
AIオペレーターは、すべての問い合わせ業務を置き換える存在というよりも、業務の中で「定型性が高く、整理しやすい役割」を担う形で活用されるケースが多く見られます。ここでは、実際に導入検討が進みやすい代表的な活用シーンを整理します。
カスタマーサポート・問い合わせ窓口
- 一次受付・用件整理
問い合わせ内容をヒアリングし、要件を整理したうえで次の対応につなげる役割です。人が対応すべき案件とそうでないものを切り分けやすくなり、対応の集中と分散を両立しやすくなります。 - 混雑時・ピーク時の対応補完
繁忙時間帯や問い合わせが集中するタイミングでも、一定水準の対応を維持しやすくなります。待ち時間の長期化を避ける補助的な役割として導入されることもあります。
公共・インフラ関連の案内業務
- 手続きや利用方法の案内
申請方法や利用条件など、あらかじめ情報が整理されている内容ではAIオペレーターが活用されやすい傾向があります。
案内内容を統一しやすく、対応品質のばらつきを抑えやすい点が特徴です。 - 営業時間外・夜間対応
人による対応が難しい時間帯の窓口として、補完的に運用されるケースもあります。緊急度の低い問い合わせを受け付け、翌営業日の対応につなぐ役割として使われることもあります。
社内向け問い合わせ・ヘルプデスク
- IT・総務系の定型問い合わせ対応
パスワード再設定や申請手続きなど、問い合わせ内容がある程度限定される業務では導入効果を見込みやすい領域です。対応ログをもとに、継続的に改善しやすい点も特徴です。 - 問い合わせ内容の整理・振り分け
社内の問い合わせを整理し、適切な担当部署につなぐ役割として活用されることもあります。担当者側の負荷軽減や対応スピードの安定化につながるケースがあります。
このように、AIオペレーターは「どのような業務を担わせるか」という視点で整理すると、自社での活用イメージがしやすくなります。
AIオペレーター導入時に押さえるべき注意点
AIオペレーターの導入では、対話を自動化すること自体ではなく、既存の業務フローの中に、どう組み込むかという視点が重要になります。ここでは、AIオペレーターを、業務を分担・実行する仕組みとして運用するために押さえておきたいポイントを整理します。
対応範囲は「業務単位」で段階的に広げる
AIオペレーターの活用を考える際、対応範囲の捉え方によって設計の方向性が大きく変わります。
多くのケースでは、業務プロセスの一部を切り出して担わせる方が、運用しやすくなります。たとえば「用件の聞き取りまで」「必要情報の案内まで」など、どこまでをAIが担当し、どこから人に引き継ぐのかを業務単位で区切って設計することで、想定外のケースで処理が滞るリスクを抑えやすくなります。
人との役割分担は「引き継ぎの瞬間」まで設計する
AIオペレーターの運用では、AIから人へ切り替わるタイミングが最も体験に影響します。
単に「途中で人に渡す」のではなく、
・どこまで情報を取得しているか
・人は何を前提に対応を始めるのか
といった点を明確にしておくことが重要です。引き継ぎ時の情報不足や二度聞きが発生すると、かえって顧客体験を損ねてしまうケースもあるため、AIオペレーターは人の対応を補助する存在として設計するという視点が求められます。
改善は「精度」だけでなく「業務の詰まり」を見る
AIオペレーターの改善というと、認識精度や応答内容ばかりに目が向きがちですが、実務では業務フロー上で詰まりが起きていないかを見ることが重要です。
・どの段階で人に切り替わっているか
・途中で離脱が多いポイントはどこか
といった観点でログを確認することで、シナリオや業務設計そのものを見直すヒントになります。また、生成AIや自然言語理解の向上により、複雑な問い合わせの整理や表現の幅を広げることも可能になっています。
導入時の課題と成功のポイント
AIオペレーターの導入には、技術面・運用面の両方で注意するべき課題があります。特に、段階的な設計とデータを活用した改善体制の確立が成功のカギとなります。
導入前の設計・シナリオ整備
まず、導入前の設計・シナリオ整備が非常に重要なポイントです。初期段階で、ユーザー視点のシナリオを作成したり、FAQの整理をすることで、顧客の利用シーンやニーズに沿った自然な会話設計が可能になります。顧客の利用シーンやニーズに沿った自然な会話設計が可能になります。その結果、ユーザーは迷うことなく目的を達成でき、自然で快適な利用体験につながります。
人との連携フローの設計
次に重要となるのが、人との連携フローの設計です。AIから有人オペレーターへの引き継ぎがスムーズであるかどうかは、CX(顧客体験)の質に直結します。「定型的な問い合わせはAIが対応し、複雑なケースは有人に引き継ぐ」といった切り分けルールを明確に設定することで、顧客は安心して利用できる対応を受けられます。
運用と改善サイクル
導入後はデータ整備と改善サイクルの構築が求められます。AIオペレーターが記録する応答ログや会話データを体系的に収集・整理し、それを基に改善を重ねることで応答精度を高められます。学習データの反映を継続的に行う体制を整えることで、AIは進化を続け、より高品質な顧客対応を実現できます。データの質と量を担保することが、AIオペレーターの進化を加速させる鍵となります。
AIオペレーター活用から、業務全体の設計へ
AIオペレーターは、一次対応の効率化や問い合わせ整理に有効ですが、導入効果を最大化するには、業務全体の中でどう位置づけるかが重要です。対応範囲や判断ポイントを整理し、人との役割分担を前提に設計することで、現場に無理なく定着しやすくなります。
一方、問い合わせ対応の前後には、情報検索、条件整理、社内システム連携など、複数の処理が関わるケースも少なくありません。このように、業務を単体のAIだけで完結させるのが難しい場面では、役割の異なる複数のAIが連携して業務を成立させるマルチAIエージェントという仕組みも有効です。
CAT.AI マルチAIエージェントは、問い合わせ対応を起点に、情報取得・判断支援・業務処理までを分担・連携させることで、業務全体をスムーズにつなぐことを目指した仕組みです。AIオペレーターの活用を検討する中で、より広い業務設計の選択肢として位置づけられます。
この流れを整理することで、対応品質の安定化や業務負荷の軽減など、具体的なメリットを把握しやすくなります。具体的な導入事例や活用パターンをまとめた資料もあわせてご確認ください。
企業の皆さまやユーザーの皆さまのIT活用を円滑化する総合的なコミュニケーションプラットフォーム、「CAT.AI」についてのご紹介資料です。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。


.jpeg)