FAQ対応はチャットボットにお任せ!導入効果と活用のポイント

FAQの管理は、Webサイト運営において重要な作業の1つです。しかし、よくある質問をすべて網羅し、わかりやすい文章でまとめるのは、想像以上に手間がかかります。
また、1度作成したFAQは、サービス内容の変更などに応じて定期的に見直す必要もあります。
FAQの作成・管理の負担を軽減し、より効率的な顧客サポートを行うためには、FAQシステムの活用だけでなく、チャットボットも効果的です。
この記事では「FAQ対応をチャットボットに任せた際の導入効果」について解説します。運用後の「チャットボットとFAQシステムの違い」や、「運用後の活用のポイント」についても紹介しているので、参考にしてください。
Index
チャットボットとは
チャットボットは、ユーザーとの対話を通じて情報を提供したり問題を解決したりするシステムです。応答機能が自動化されているため、24時間365日いつでも利用できます。以下の3つの種類があります。
- シナリオ型
- AI型
シナリオ型はあらかじめ設定したシナリオに従って応答しますが、AI型は自然言語処理を活用して柔軟に対応します。複雑な問い合わせにも対応可能です。
AI型チャットボットについては以下の記事でも詳しくご紹介しています。
AIチャットボットとは?基本的な仕組みと活用がおすすめのシーン
FAQシステムとは
FAQシステムは、良くある質問とその回答を一覧で提供する仕組みです。簡潔で視覚的にわかりやすく提示できる点が特徴となっています。以下の3種類があります。
- 顧客向けFAQシステム
- 社内向けFAQシステム
顧客向けFAQシステムは、企業のホームページで多く採用されています。問い合わせにも対応しているため、利用した経験のある方も多いのではないでしょうか。
一方社内向けFAQシステムは、社員やスタッフからの疑問を解消するために社内ヘルプデスクなどで活用されています。気軽に問い合わせができる点から、近年多くの企業から注目を集めているFAQシステムです。
また、顧客対応の際にオペレーター間でのナレッジの共有を目的とした、コールセンター向けの機能が搭載されているFAQシステムもあります。自社の状況に合わせて、最適なものを選ぶと効果的です。
チャットボットとFAQシステムの違い
チャットボットとFAQシステムは似ているようで異なる部分が多くあります。特に大きな違いは下記の3つです。
- インターフェース
- 想定ユーザー
- 回答に辿り着くまでの速さ
インターフェース
チャットボットとFAQシステムは、まずインターフェースが大きく異なります。チャットボットは対話型のインターフェースを持ち、ユーザーが質問を入力すると即座に応答します。一方のFAQシステムは、リストや検索結果形式で情報を提供する形です。
チャットボットは即時応答してくれるので、ユーザーにとって親しみやすいシステムです。FAQシステムは、整理された情報を求めるユーザーに適しています。
想定ユーザー
チャットボットとFAQシステムは、想定しているユーザーも異なります。
チャットボットが向いている主な層は、テキスト入力やチャットの操作に慣れている方や端的に回答を得たい方などです。
FAQシステムが向いている主な層は、自分で情報を探すことに慣れた方や、的確な回答を得たい方などです。FAQシステムは提供できる情報量が多いため、詳細な回答を提示できます。
そのため、導入の際はどのようなユーザーをターゲットにするのかが重要になってきます。
回答に辿り着くまでの速さ
チャットボットとFAQは回答に辿り着くまでの速さも大きく異なります。
チャットボットは検索ワードからユーザーが知りたい内容を予測して選択肢を提示するので、ストレスなく回答に辿り着けます。
一方、FAQシステムはユーザーが自ら必要な情報を検索するため、欲しい情報に辿り着くのに時間がかかる点がネックです。ユーザーが探しやすいように、カテゴリー分類の仕方など検索しやすい構成にすることが求められます。
チャットボットとFAQシステムの共通点
チャットボットとFAQシステムには違いがある一方で、以下のような共通点もあります。
- 顧客満足度を向上できる
- データの準備が必要
- 導入後のメンテナンスが必要
ユーザーの自己解決を促進できる
チャットボットとFAQシステムは、問い合わせせずに自己解決を促す役割が共通点です。
24時間365日いつでも利用できるため、時間や場所を問わず問題を解決できます。オペレーターに繋がらない、メールの返信を待たされるといった不満も解消できるため、顧客満足度の向上に繋がります。
データの準備が必要
チャットボットもFAQシステムも、有効活用するためには必要なQ&Aなどのデータをあらかじめ準備する必要があります。
データが少ないと、問い合わせに答えられないケースが増え、ユーザー満足度にも大きく影響します。まずは事前によくある質問を整理し、多くのデータを用意しておくことが重要です。
事前の準備が万全であるほど、ユーザーの満足度も高まります。
導入後のメンテナンスが必要
チャットボットとFAQシステム、どちらも運用中にデータの追加や更新が必要です。導入して終わりではなく、実際の利用率などのデータを分析し、定期的にメンテナンスを行うことが重要です。ユーザーのニーズに合わせてデータを改善することで、システムの使いやすさを維持できます。
導入時の準備だけではなく、継続的にメンテナンスをして顧客満足を高めていきましょう。
FAQ対応をチャットボットに任せる4つの効果

チャットボットでFAQ対応を行うことも可能です。そうすることによって、以下のような効果があります。
- 会話をするように検索できる
- 顧客の目の付きやすい場所に設置ができる
- 既存のFAQや問い合わせフォームに誘導できる
- システムの一元化
会話をするように検索できる
チャットボットは、テキストによる会話形式で、AIとやり取りが可能です。入力された文章からAIが推測してくれるため、ユーザーが自然な言葉で質問できます。
チャットを行う感覚で質問を投げかけることができるため、初心者にも使いやすい傾向にあります。特にAI型のチャットボットであれば、「この商品の保証期間は?」といった曖昧な質問にも、質問に答える前にチャットボットによって商品を特定したり、顧客情報を特定することで対応可能になる場合があります。
ユーザーが抱える課題が不明瞭な場合でも、必要な情報を得られやすいと言えます。
顧客の目の付きやすい場所に設置ができる
チャットボットは様々な場所に設置できるため、サポートページだけでなく、商品ページや購入手続きページなどユーザーが疑問を持ちそうな場所に複数設置しておくことで、必要なときにすぐ使えます。自動応答のため即座に回答も表示されるため、顧客体験の向上に繋がります。
チャットボットの回答で問題が解決しない場合は、有人オペレーターへの切り替えなど対策をしておくことで、チャットボットで解決しないという不満を防ぐことも可能です。
既存のFAQや問い合わせフォームに誘導できる
チャットボットでは、必要に応じて既存のFAQや問い合わせフォームへのリンクも提示可能です。もし満足できる回答を得られなかったとしても、適切な情報にアクセスしやすい状態を構築できます。
また、問い合わせ内容が詳細であったり難しかったりする場合には、フォームへの記入を促して有人での対応をするといった形も良いでしょう。
既にあるFAQや問い合わせフォームと連携させることで、チャットボットは更に効果的に運用できます。
システムの一元化
既存のFAQシステムと連携することで、それぞれ別々に管理している場合に比べ、管理工数を削減することが可能です。
双方の閲覧履歴やデータを連携することで、FAQの更新や拡充といった管理の手間が削減できます。
また、FAQは網羅的に情報を掲載することができますが、閲覧数が多いFAQのみチャットボットで表示することで、より顧客のニーズに合わせて自己解決を促進しやすくなるでしょう。
チャットボットでFAQシステムを活用する際の4つのポイント
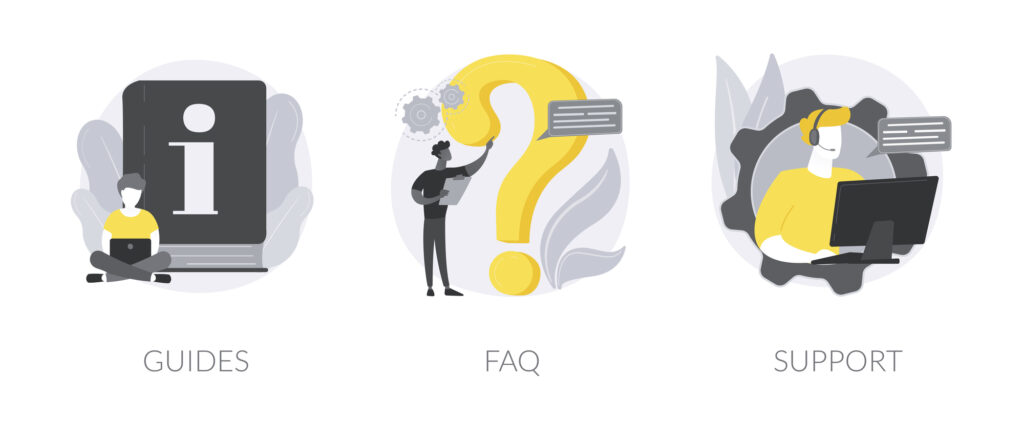
チャットボットでFAQシステムを活用する際のポイントは以下です。
- 導入の目的を明確にしておく
- ユーザー目線のFAQを用意する
- 改善を繰り返す
- その他のお問い合わせ窓口を明記する
導入の目的を明確にしておく
チャットボットを導入する際には、目的を明確にしておくようにしましょう。一口にチャットボットといっても、ツールによって出来ることが異なります。顧客向けか社内向けかなどでも変わるため、導入の目的に沿ったものを選ぶ必要があります。
どのような運用をしたいのか方向性を決めた上で、チャットボットを活用するようにしましょう。
ユーザー目線のFAQを用意する
チャットボットで使用するFAQは、ユーザーが理解できるように整える必要があります。どれだけ情報を網羅できていたとしても、回答文が難しいと利便性が良いとは言えません。
特に気を付けたい点は以下の2つです。
- 専門用語が多い
- 文章が長い
特に多いのは、専門用語ばかりでユーザーが理解できないケースです。FAQを作成している人にとってはわかりやすい言葉であっても、ユーザーにとってはわかりにくい場合があります。そのため、FAQはユーザーが理解しやすいかどうかを意識することが大切です。
また、チャットボットはチャットアプリのように表示されます。長文を表示すると読みにくく感じるユーザーもいるため、端的にまとめつつ、情報量が多くなりそうな場合は、必要に応じて詳しく解説しているWebページなどに遷移できるようにURLを掲載することも効果的です。
ユーザーの理解度やニーズに合わせた文章を作成して、わかりやすさと読みやすさを意識することが重要です。
改善を繰り返す
準備を万全にしてFAQを作成しても、最初から完璧なものは作れません。チャットボットを使って運用を始めると、作成時には見えなかった以下のような部分が見えてきます。
- 不足情報
- 伝わりづらい表現や回答
- 古い情報
こうした情報を基に、定期的に登録されているデータの見直しをしていくようにしましょう。チャットボットで回答できなかったという問い合わせがあれば、FAQ追加の検討が必要です。
電話やメールでの問い合わせも参考にして、定期的に改善をしていきましょう。
その他のお問い合わせ窓口を明記する
チャットボットがすべての質問に対応できない場合に備え、その他の問い合わせ窓口を明示しておくのも重要です。
例えば、電話やメールなどの問い合わせ先といった情報です。電話やメールへの問い合わせ削減を意識しすぎて分かりづらい場所に情報を掲載してしまうと、問い合わせが解決できないため、満足度に大きく影響してしまうので注意しましょう。
FAQ対応はチャットボットに任せて効率的に運用しよう
チャットボットとFAQシステムは、それぞれ違う特徴があります。両者の特徴や違いを理解し、適切に組み合わせれば、企業と顧客の双方にメリットをもたらしてくれるでしょう。
トゥモロー・ネットが提供するCAT.AIは、ボイスボット(音声対話AI)とチャットボット(テキスト対話AI)を同時に使用できる最新型の「ナビゲーション型」対話AIです。
ボイスボットの利点とチャットボットの利点を最大限に活かし、「聴覚」と「視覚」でわかりやすく「ナビゲーション」することで、初めて使うユーザーでもカンタンに解決に導くAIチャネルです。
簡単にデモ体験も実施いただけますので、是非お問い合わせください。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。


.jpeg)




