生成AIとの連携でボイスボットはどう変わる?企業が導入すべき理由と注意点
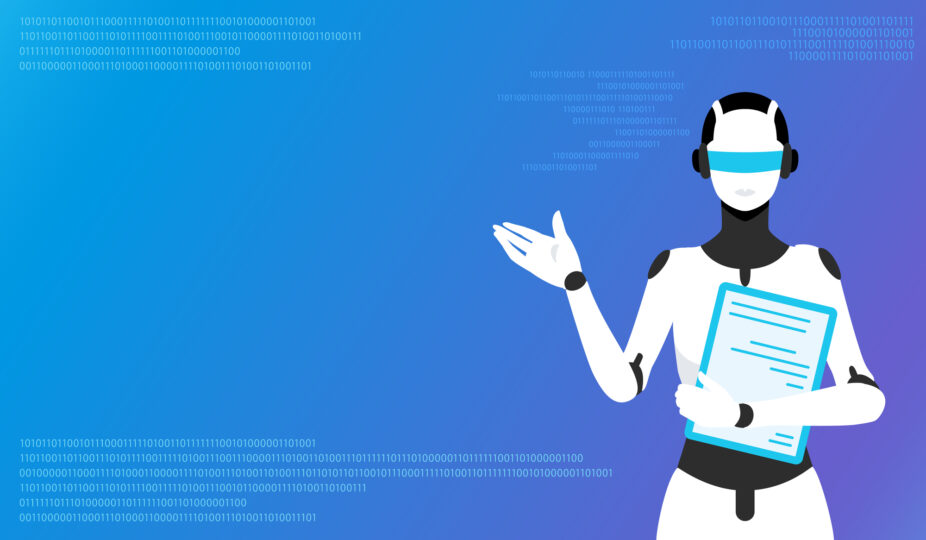
従来のボイスボットは定型的な業務の効率化に特化しており、コールセンターを中心とした電話対応の自動化に貢献してきました。
しかし、将来的には生成AIとボイスボットを連携することで、より人間に近い対応がAIによって可能になるかもしれません。
今回は、生成AIの概要を始め、ボイスボットと生成AIを連携するメリットと企業が導入すべき理由、そして企業で活用する際の注意点と対策について解説します。
生成AIに興味をお持ちの方はもちろん、企業への導入を検討されている方にも参考にしていただければ幸いです。
Index
生成AIとは
本題に入る前に、まずは生成AIの概要について簡単に理解しておきましょう。生成AIとは、新しいコンテンツを自動で生成することができる人工知能のひとつであり、生成系AIやジェネレーティブAIと呼ばれることもあります。
従来のAIは学習データの中から最も適切な回答を「検索」していたことに対し、生成AIは新たな回答をAI自身が「生成」することができるという大きな違いがあります。
生成AIの種類
生成AIは学習したデータに基づいて、テキストだけではなく、画像や音楽などの新たなコンテンツを作り出すことができますが、生成できるデータの種類は生成AIごとに決まっています。ここでは、代表的な生成AIの種類について簡潔に解説します。
- テキスト生成AI
- 画像生成AI
- 動画生成AI
- 音声生成AI
それぞれ見ていきましょう。
テキスト生成AI
テキスト生成AIは、ユーザーがテキストで入力した質問などに対し、内容に応じた回答文を自動で生成することができます。ビジネスシーンではレポートやコンテンツの作成、文章要約などで活用されています。
画像生成AI
画像生成AIは、ユーザーがテキストで指示を入力すると、その意図に沿った画像を生成することができます。従来、画像を制作するには専門的な知識や技術が必要でしたが、画像生成AIによって誰でも簡単に画像を制作できるようになりました。
動画生成AI
動画生成AIは、テキストと時には画像も組み合わせて指示を入力すると、意図に沿って動画を生成することができます。動画生成は、他の種類の生成AIよりも高度な処理が求められるため、生成AIの中では最も実現難易度が高いと言われています。
音声生成AI
音声生成AIは、人間の音声データを学習させることで、新たな音声を生成することができます。そして単に文章を読み上げるだけでなく、喜怒哀楽の感情に合わせた表現が可能という大きな特徴があります。
ボイスボットとは
ボイスボットとはAIを搭載した自動応答システムで、主にコールセンターなどの顧客対応業務の代行に活用されています。ボイスボットを活用することによって、オペレーターの負担軽減や業務効率化、顧客満足度の向上といった効果を生んでいます。
ただし、ボイスボットに搭載されているのは生成AIではないことがほとんどであり、「定型的な業務の自動化には適しているが、複雑な問い合わせには対応できない」などの課題もあります。
【関連記事】ボイスボットとは?AIに顧客対応を任せるメリットと注意点について
ボイスボットと生成AIの連携について
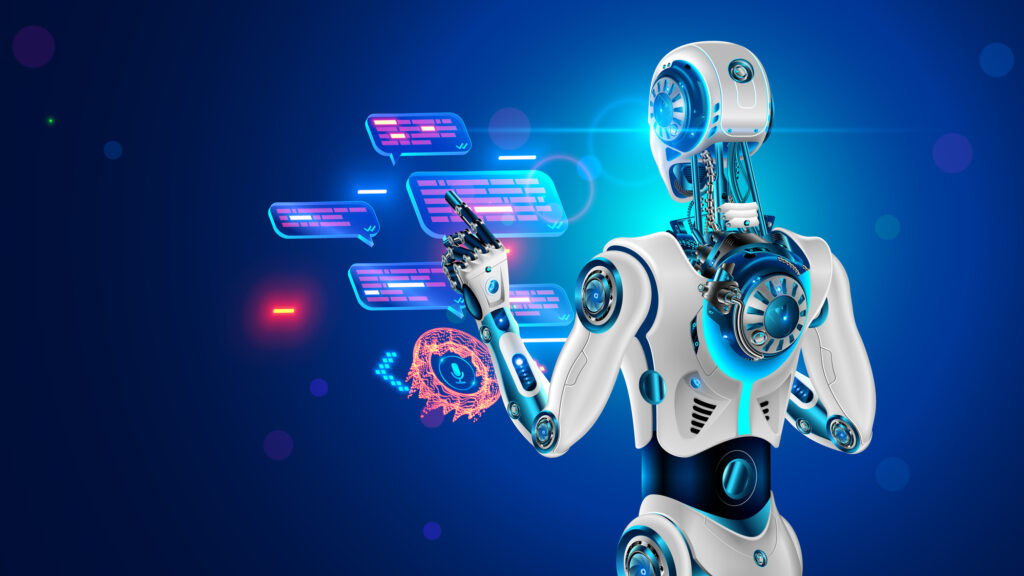
生成AIのカスタマーサポート領域での活用について期待が高まっています。主にWEB上の顧客対応や、オペレーター支援などでの活用が進んでいますが、一方で、電話の問い合わせ自動化として昨今注目されているボイスボットと生成AIの連携はあまり進んでいないのが現状です。
理由としては、生成AIで生成されるテキストや情報は、ときには膨大な情報になることがあります。この情報を全て音声に変換して使用するというのは現実的ではなく、ボイスボットで生成AIを活用することは、技術的には可能ですが、サービスとしての活用にはハードルがある状況です。
将来的に生成AIとボイスボットの連携が進めば、ボイスボットで「より人間に近い対応」ができるようになります。例えば、下記のようなことが期待できます。
- 感情を予測することができる
- 意図を理解することができる
- 顧客に合わせた対応ができる
生成AIとボイスボットの連携が実現すると、ボイスボットがどのように進化できるのか詳しくご説明します。
感情を予測することができる
生成AIは感情を持つことはありませんが、学習したデータを元に発話内容からユーザーの感情を予測することができます。これは「感情認識」という技術によるものであり、音声のトーンや速度、言葉選びなどから喜びや怒り、悲しみなどの感情を予測します。
これにより、ボイスボットは従来のAIでは困難だった「ユーザーの感情を予測した上での対応」が可能となり、より人間に近い対応に繋がります。
意図を理解することができる
従来のAIが事前にプログラムされたスクリプトやキーワードを元に回答を提示していたのに対し、生成AIは高度な「自然言語処理技術」によってユーザーの意図を理解して回答を提示することができます。
自然言語処理技術とは、私たちが日常で使っている言語や音声を認識し、内容を理解、回答を生成する技術です。話し言葉など自然言語特有の曖昧な表現も解析し、発話者の意図を理解することができます。
これにより、複雑な問い合わせへも対応できる可能性が高まり、従来のAIに比べ、より柔軟に有人オペレーターに近い対応ができると考えられます。
顧客に合わせた対応ができる
生成AIは学習したデータだけではなく、顧客の行動履歴なども参照した上で回答を生成するため、それぞれの顧客に合わせた柔軟な対応ができるという特徴があります。
例えば「先日購入した商品」という抽象的な表現であっても、直近の購入履歴を元に該当商品を特定することが可能です。これにより、ユーザーは自ら詳細な情報を提示することなく、手間やストレスが少ないコミュニケーションが実現します。
企業が生成AIと連携したボイスボットを導入するメリット
生成AIとボイスボットを連携することで、より人に近い自然な顧客対応を実現することができます。これにより、企業は以下のようなメリットを得ることができます。
- 大幅な業務効率化
- さらなる顧客満足度向上
それぞれ見ていきましょう。
大幅な業務効率化
生成AIと連携したボイスボットによって、大幅に業務を効率化することができます。その理由の一つとして、従来よりもボイスボットで自動化できる顧客対応の幅が広がることにより、今まで以上にその他のコア業務に人的リソースを割くことが可能です。
もう一つの理由は、メンテナンス部分にあります。従来のAIが搭載されたボイスボットでは、新たな情報を学習させるためのデータの用意や、人による仮説の立案や対策の実行が欠かせませんでした。一方、生成AIの場合はユーザーとのやり取りからも学習できるほか、対応を繰り返す中で回答精度が高まるよう自ら処理することができます。
もちろん回答に誤りがないかなど、人による定期的なチェックは必要ですが、メンテナンスにかかる手間は軽減する傾向にあります。
さらなる顧客満足度向上
生成AIと連携したボイスボットでは、従来のボイスボットでは対応できなかった問い合わせにも対応できる可能性が高いと言えます。これにより、顧客は有人オペレーターに繋がるのを待つことなく即座に回答を得られることが増え、顧客満足度をさらに向上することが期待できます。
また、顧客に合わせたパーソナライズ対応により、顧客体験が高まり、満足度向上にも繋がると言えます。
このような理由から、生成AIと連携したボイスボットは、従来のボイスボット以上に顧客満足度を向上させられるでしょう。
生成AIと連携したツールを企業で活用する際の注意点

生成AIと連携したツールの利用は、業務効率化や顧客満足度向上といったメリットがありますが、活用する際には注意すべき点も存在します。
ボイスボットやチャットボットに限らず、生成AIツールを使用する上で押さえておきたい
主な注意点は以下です。
- 誤った回答を生成するリスクがある
- 個人情報漏洩のリスクがある
導入を検討する際には知っておくべき重要な内容ですので、しっかりと理解しておきましょう。
誤った回答を生成するリスクがある
生成AIは必ずしも適切な回答を生成する訳ではありません。生成AIは事前に用意したデータに加え、ユーザーがやりとりを行う中で入力した内容や、オープンデータを参照して回答を生成するため、偏った知識や情報が蓄積されていった場合、誤った回答を生成するようになる懸念があります。
個人情報漏洩のリスクがある
生成AIとのやりとりの中で個人情報に該当するようなデータを提供した場合に、他のユーザーとのやりとりにおいてその個人情報が表示されてしまう恐れがあります。
また、生成AIと連携したボイスボットは企業が保有するあらゆる情報を参照できるため、まだ公にしていない企業情報が顧客とのやりとりで流出してしまうことも考えられるため対策が必要です。
生成AIと連携したツールを安全に運用するために
ここでは、前述のようなリスクを予防し生成AIツールを安全に運用するために重要なポイントについて解説します。主なポイントは以下の通りです。
- 定期的なメンテナンスを怠らない
- オープンデータの使用制限があるツールを選ぶ
- 社内のセキュリティ意識を高める
定期的なメンテナンスを怠らない
生成AIが誤った回答を生成するのを防ぐために、定期的にツールの運用状況を確認し、「生成した回答に誤りがないか」や「学習・参照したデータの量や信頼性に問題はないか」といったチェックや調整などのメンテナンスを怠らないようにしましょう。
ただし、このようなメンテナンス作業には専門的な知識がある方が安心ですので、自社に知見がない場合にはメンテナンス作業も行ってくれるベンダーを選定することをおすすめします。
オープンデータの使用制限があるツールを選ぶ
オープンデータとは誰もが閲覧できるデータを意味します。オープンデータの使用が制限されていないと、あらゆる情報を参照して回答が生成されてしまうため、事実に基づかない情報や、企業に関係のない情報も回答してしまう等、ハルシネーションリスクが発生します。オープンデータを使用しないような制限ができる機能を持ったツールを選ぶことで、ハルシネーションリスクを最小限に抑えることができます。
社内のセキュリティ意識を高める
生成AIを扱う際には、社内のセキュリティ意識を高めるようにしましょう。顧客や社員の個人情報を含めたデータの管理方法や、生成AIのリスクについて教育するなど、一人ひとりのセキュリティ意識を高めることが非常に大切です。
ボイスボットは生成AIと連携することで、より人間に近い対応が可能になる
ボイスボットを生成AIと連携させることによって、感情の予測や意図の理解、パーソナライズした対応など、従来のボイスボットよりも人間に近い対応ができるようになると考えられます。
これにより、企業は更なる業務効率化や顧客満足度向上といったメリットを得ることができるでしょう。ただし、生成AIはその運用方法に注意しなければ誤った回答を生成する懸念や、個人情報の取り扱いに対するリスクがあります。
このようなリスクを避けるためには、定期的なメンテナンスやツール選び、セキュリティ意識を高めることが重要です。
生成AIと連携したボイスボットツールが実用化され、本格的に企業への導入が進むときには、その特徴と注意点をしっかりと理解し、安全性の高いツールを選定するようにしましょう。
生成AIと連携したツールならCAT.AI GEN-Botがおすすめ
トゥモロー・ネットが提供するCAT.AI GEN-Botは、生成AIと連携し企業が保有するあらゆるデータベースに基づいてテキストだけではなく、画像やフォームも使いながら適切な回答を作成・提示し、パーソナライズした対応で問題解決に導くことができるシステムです。
高度なデータベースとBot機能でオープンデータ使用を制御し、生成AIの課題でもあるハルシネーションの発生を最低限に留め適切な回答を提供することに加え、独自開発のNLP(自然言語処理)エンジンを搭載し、データ検索の精度を向上します。
企業の公式サイトやアプリ、チャットでの問い合わせ・FAQなどのフロントチャネルとしての活用に加え、社内規定やガイドライン、専門職のナレッジ統合ツールなどの従業員サポート・社内ヘルプデスクとして利用することができますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。








