ボイスボットで電話対応を自動化|対話型AIの活用事例を紹介します
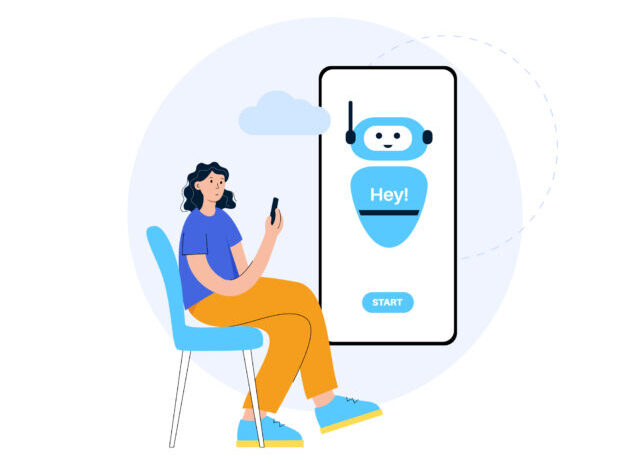
「FAQや問い合わせフォームを充実させたけど電話への問い合わせが減らない」
「人材不足で対応しきれない」
「オペレーターの負担が大きく、離職率が高い」
このような課題を抱えている企業は多いのではないでしょうか。
近年、チャットボットを始めとした対話型AIが多くの企業に導入されています。しかし、依然として電話での問い合わせ件数が削減されず、悩みの種になっている企業も少なくありません。
そこで今回は、対話型AIの中でも電話対応を自動化できる「ボイスボット」について詳しく解説します。記事後半では、電話対応自動化におすすめのツールや導入事例もご紹介しますので、是非最後までご覧ください。
Index
対話型AIとは
対話型AIとは、人とコンピューターが自然なやりとり(対話)ができる技術のことです。
人と自動でやりとりを行うAIを指し、テキストで行うチャットボットや、音声で行うボイスボットがあります。
なぜ電話での問い合わせは減らないのか
トランスコスモス株式会社が2024年に実施した調査によると、問い合わせをする際に一番最初に選ぶチャネル(手段)は、20~70代どの世代においても電話が最も多いという結果が出ています。
出典:消費者と企業のコミュニケーション実態調査2024-2025 徹底解説|trans+(トランスプラス)
また、当社が2024年に行った調査では、問い合わせに電話を選ぶ理由として多いのは「Webサイトで調べたがわからなかった」「複雑な内容だったので人と話したかった」「合っているか不安だった」などが挙げられました。
WebサイトのFAQやチャットボットを利用するユーザーも若年層を中心に年々増加してはいますが、それでも「電話が最も解決に繋がるチャネル」として認識しているユーザーが未だ多いと言えます。
ボイスボットで電話対応を自動化できる
電話での問い合わせが削減されないのであれば、電話対応を自動化してはいかがでしょうか。ボイスボットを導入することで、よくある質問や定型的な手続き対応などの問い合わせ対応を自動化することが可能です。
ボイスボット(AI)にあらかじめ問い合わせ対応に必要な知識(データ)を学習させることで、ユーザーからの問い合わせに対し最適な回答を提示し、AIだけでよくある質問や定型的な手続き対応などの問い合わせ対応が完結できるようになります。
これにより、有人オペレーターの対応件数が削減されるため、電話での問い合わせ件数が変わらずとも業務効率化や人材不足解消、オペレーターの負担軽減が期待できます。
次項では、具体的なボイスボットの活用事例をご紹介します。
ボイスボットの活用事例
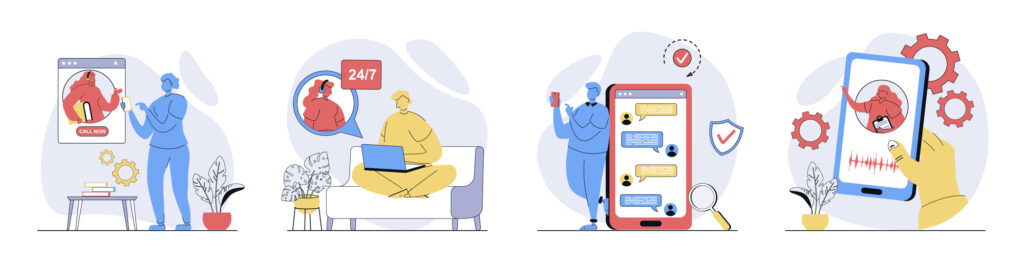
ボイスボットはコールセンター以外にも、さまざまな場面で活用されています。例えば以下のようなものです。
- 飲食店
- 宿泊施設
- 旅行代理店
- 自治体
では、導入先でボイスボットはどのような対応をしているのでしょうか。ここでは業務内容に焦点を当てた具体的な活用事例をご紹介します。主な活用事例は以下の通りです。
- 問い合わせ対応
- 予約受付・管理
- 一次受付やコールバック予約
それぞれ見ていきましょう。
問い合わせ対応
最もオーソドックスな活用方法の一つが、問い合わせ対応です。FAQによくある「営業時間」や「料金」、「サービス内容に対するもの」などの定型的な問い合わせ対応を自動化することができます。また、パンフレットなどの「資料請求」受付や、製品情報・サービスプランなどの情報を案内するような使い方も可能です。
予約受付・管理
飲食店やホテルなどの予約受付やリマインド通知を自動化するという活用方法です。希望日時や予約名をヒアリング、予約受付を完了したのち、予約確定やリマインドの連絡をSMSなどで自動で行うという使い方もできるため、電話対応以降のオペレーターの作業も自動化することに繋がります。
ボイスボットによる電話予約の自動化は、AI接客における代表的な活用例のひとつです。
飲食・宿泊業界をはじめとした具体的な成功事例については、「AI接客の成功事例(飲食・宿泊を含む)」 もあわせてご覧ください。
一次受付やコールバック予約
ボイスボットだけで完結できない問い合わせが来た際に、ボイスボットが問い合わせ内容や折り返し希望日時など必要事項をヒアリングし、一次対応を自動化することも可能です。有人オペレーターが他の対応中ですぐに転送できない場合などに、顧客を待たせることなく一次対応ができるため、回線の混雑回避や顧客の待ち時間削減にも効果が期待できます。
これにより、回線の混雑回避や顧客の待ち時間削減にも効果が期待できます。
ボイスボットの課題
ボイスボットにも他のツールと同様に課題があります。主な課題は以下の通りです。
- 周囲の環境によって精度が変わる
- 名前や住所などを正確に反映することが難しい
それぞれ見ていきましょう。
周囲の環境によって精度が変わる
周囲に雑音が多いなど、発話者の声を聞き取りづらい環境では音声を認識する精度が落ちてしまいます。有人オペレーターであれば聞き取りにくい旨をすぐに伝えるなどの対処も可能ですが、ボイスボットはそのような柔軟な対応は難しいため、ヒアリング内容に誤りが出てしまうことも考えられます。
名前や住所などを正確に反映することが難しい
名前や住所などは漢字での表記が必要なため、音声だけで正確に反映することは難しいです。有人オペレーターでの対応であれば、「どのような漢字ですか」といった質問などで補うことが可能ですが、ボイスボットで対応するには必要な学習データがあまりにも膨大になるため現実的ではありません。
このように、ボイスボットにも課題があります。特に名前や住所などを正確にヒアリングする必要がある業種の方は、「ボイスボットで電話対応の自動化は難しそうだ」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方には「ボイスボット」と「チャットボット」を融合した「CAT.AI CX-Bot」がおすすめです。CAT.AI CX-Botは、ヒアリング内容の複雑さから今までボイスボットの導入を諦めていた企業でも導入されており、大きな効果を発揮しています。
ボイスボットとチャットボットの良いとこどり!「CAT.AI CX-Bot」をご存知ですか?
また、ツールの運用には欠かせない「サポート体制」も充実しており、トラブル対応は当然のこと、日々の利用状況の分析や改善点の提案を始め、ツールの導入効果を最大限に発揮するためのトータルサポートを行ってくれます。
【導入事例】AI対応完了率96%を達成「東京ガス株式会社」
東京ガス株式会社では、お客様受付の約半数を占める「ガス開閉栓受付」をCAT.AI CX-Botで自動化しています。
以前からWeb受付の改善に力を入れていましたが、そもそもWebサイトを見ないお客様も多く、CAT.AI CX-Botを導入する何年も前からボイスボットを検討されていました。しかし、名前や住所、お客様番号など聴取内容が複雑なこともあり、それまでの一般的なボイスボットでは「完全な自動化は不可能」と言われていました。
しかしCAT.AI CX-Botでは音声での案内に加え、電話をしながらショートメッセージに移行し名前や住所などの必要事項をテキストで入力できることから、問い合わせ対応の自動化が実現。
導入後わずか1か月で、AI対応完了率(AIだけで問い合わせ対応が完結した割合)は驚異の96%を達成し、大きな効果を発揮しています。
東京ガス様の事例はこちら
電話対応件数の削減ならボイスボットを導入しよう
「いくらWebサイトを充実させても、電話対応が減らない」と悩んでいる企業は多いと思います。それは、これだけ問い合わせフォームなど対応チャネルが充実した現代においても、「電話が最も解決に繋がるチャネル」として認識しているユーザーが大多数であることが大きな原因です。
電話対応が減らないのであれば、ボイスボットで電話対応を自動化してみてはいかがでしょうか。ボイスボットを導入することで、定型的な問い合わせ対応や予約受付・管理を自動化することができるほか、コールバックで混雑緩和にも活用することが可能です。
しかし、ボイスボットには音声認識に対する課題もあるため、音声だけでの対応は不安という方は「CAT.AI CX-Bot」を検討してみてください。
「CAT.AI CX-Bot」は音声とテキストを駆使し、ユーザーが抱える課題に対しスムーズに、ストレスフリーなサクセス体験を提供し、AI対応の完了率を向上していきます。独自開発のNLP(自然言語処理)技術を搭載し、AIであってもヒトと話すような自然なコミュニケーションを実現できることが特徴です。
当社の専門デザイナーがCX(顧客体験)と豊富なAI機能を駆使し、クライアント企業様のAIコミュニケーションをデザインします。簡単にデモ体験も実施いただけますので、チャットボットの導入をご検討の際は是非お試しください。
ボイスボットの選び方や仕組みなどに関しては以下の記事で詳しく解説していますので、是非ご覧ください。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。


.jpeg)




