チャットボットだけでは限界?運用課題とマルチAIエージェントでの解決策
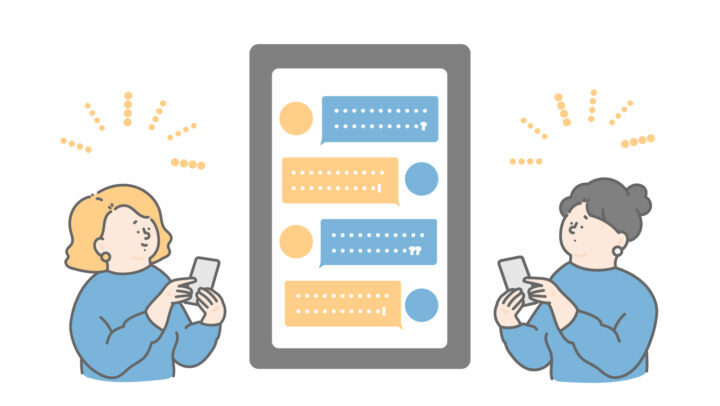
近年、企業の顧客対応や業務効率化の現場では、チャットボットの導入が一般的になりました。定型的な質問への即時回答や、問い合わせ件数の削減などに一定の効果を発揮してきた一方で、「複数の部署にまたがる複雑な業務」「状況に応じた柔軟な対応」といった高度なニーズには限界があります。
こうした課題を解決する次世代のアプローチとして注目されているのが 「マルチAIエージェント」 です。マルチAIエージェントとは、複数のAIがそれぞれの役割を持ち、連携しながら全体の業務を自動化・最適化していく仕組みです。従来のチャットボットが「個別の問いに答える」役割にとどまっていたのに対し、マルチAIエージェントは「業務全体を俯瞰し、協調して解決に導く」点が大きな特徴といえます。
この記事では、チャットボットが抱える限界を整理したうえで、マルチAIエージェントがどのようにそれを乗り越え、企業の業務変革を支援するのかを解説します。記事を読み終える頃には、チャットボット運用での課題や限界を把握し、業務改善や自動化を進めるために、どのような解決策を検討すべきかが具体的にイメージできるようになります。
Index
チャットボット運用でよくある6つの課題
チャットボットは便利なツールですが、運用方法や体制によっては期待した効果が得られないことがあります。ここでは、企業が陥りやすい代表的な課題を6つに整理しました。自社で同じような問題が起きていないか、確認しながら読み進めてみてください。
1. 導入効果が見えにくい
導入後に「問い合わせ件数が減らない」「顧客満足度が向上していない」と感じることがあります。これは導入前の目的や指標が曖昧なまま運用を始めてしまったことが原因です。
例えば「問い合わせを30%削減する」「FAQ解決率を50%以上にする」といった目標を設定していなければ、成果を判断できません。目的とKPIを明確にし、定期的に効果を可視化する仕組みが欠かせません。
2. 運用体制が整っていない
チャットボットは導入して終わりではなく、FAQ更新やシナリオ改善、学習データの追加が必要です。
しかし、運用ルールや情報共有の仕組みが整っていないと、改善が後回しになり効果を発揮できません。専任担当を置く、複数人でチームを組むといった体制づくりが重要です。
3. 回答精度が低い
ユーザーが求める回答が得られない場合、利用はすぐに減少します。主な原因は以下のとおりです。
- FAQが不足している
- シナリオ設計が不十分
- AIへの学習データが不足している
利用状況や質問傾向を分析し、FAQ・シナリオ・学習データを定期的に更新することが精度向上につながります。
4. チャットボットが利用されない
導入しても「そもそも存在に気づかれない」「利用方法がわかりにくい」という理由で活用されないことがあります。
改善のためには、チャットボットのアイコンを目立つ位置に配置する、サイト内で導線を工夫する、使い方をわかりやすく提示するといった工夫が有効です。
5. チャットボットの離脱率が高い
対話が途中で終わってしまう原因は以下のようなものです。
- 回答までに時間がかかる
- 必要な情報にたどり着けない
- 会話の流れが不自然
解決のためには応答速度を改善し、ナビゲーションをわかりやすく設計するなど、ユーザー体験を意識した改善が必要です。
6. メンテナンス作業に時間を割けない
チャットボットは最新情報を維持するために更新が欠かせません。しかし他業務が優先され、更新作業に手が回らないこともあります。
社内リソースが不足している場合は、外部ベンダーへの運用委託や運用サポート付きのサービス利用も有効な選択肢です。
チャットボット運用の課題を解決する具体的な方法

課題を把握したら、次は実際の運用でどのように改善できるかを見ていきましょう。ここでは、先ほど挙げた6つの課題を踏まえた具体的な取り組み例をご紹介します。実際に改善策をどのように実行できるかの参考にしてください。
1. 導入後の状態を可視化する
チャットボット導入前に設定した目標に基づき、KPIを定期的に確認しましょう。
例えば、問い合わせ件数の削減率やFAQ解決率、ユーザーの離脱率、顧客満足度の変化などです。
数値を可視化することで、「どこが改善されているか」「どこを優先して改善すべきか」が明確になり、運用の方向性を判断しやすくなります。
2. 離脱ポイントを分析・改善する
ユーザーがチャットボットを途中で離脱する原因を特定し改善します。
例えば、回答まで時間がかかる場合や専門用語が多すぎる場合、応答速度を短縮したり、わかりやすい表現に置き換えたりすることで効果的に改善できます。
可視化されたKPIや運用データを活用して離脱ポイントを分析することで、優先度の高い改善策を導きやすくなります。
3. チャットボットの回答精度を上げる
回答率や正答率が低い場合は、学習データやシナリオを見直し、不足しているデータを追加しましょう。
運用データをもとに改善を繰り返すことで、精度の高い回答が可能になり、ユーザー満足度も向上します。
このステップは、可視化・分析で把握した課題を実際に解消するための具体的な手段です。
4. 運用体制を見直す
担当者やチームを明確にし、定期的な更新・改善のフローを整えることが重要です。
負担の分散や知識の属人化防止の観点から、チームで運用することが望ましいといえます。
5. コールセンターとも連携する
チャットボットだけでは対応できない問い合わせや、有人対応を希望するユーザーもいます。
自動で有人対応に切り替えるフローや、他システムとの連携を可能にする体制を整えることで、ユーザー体験を損なわずに対応できます。
6. 運用をアウトソーシングする
社内リソースや専門知識が不足している場合は、外部の専門業者に運用を委託するのも有効です。
FAQの更新、シナリオ改善提案、AIの学習チューニングなどのサポートがあるツールを活用することで、効率的かつ精度の高い運用が可能になります。
チャットボットの限界とマルチAIエージェントによる解決策
これまで紹介した運用改善策を行えば、チャットボットは一定の効果を発揮できます。しかし、従来のチャットボットには構造的な制約もあります。
- 単一の目的に特化しているため、複雑な問い合わせや複数タスクの連携には弱い
- FAQやシナリオに基づく対応が中心で、柔軟な応答が難しい
- 運用や改善作業の多くが人手に依存しており、工数負担が残る
つまり、従来のチャットボットでは「ある程度の自動化はできるが、業務全体を包括的に効率化する」ことは難しく、複数の部門やシステムと連動した高度な対応や、ユーザーの意図を柔軟にくみ取った対応には限界があります。
こうした課題を解決できるのが、複数のAIエージェントが連携して動作するマルチAIエージェント型の仕組みです。
- 単一のAIでは対応しきれなかった複雑なタスクも、連携するAIが分担して処理
- ユーザーの意図を多角的に判断し、最適な回答や手続きを自動で提示
- 運用や改善作業の多くをAIが補助し、人手の負担を軽減
従来のチャットボットで課題を感じている場合、マルチAIエージェントの仕組みを取り入れることで、運用負荷を減らしつつより高品質な顧客体験を提供することが可能です。
まずは自社で抱える課題を整理し、どの部分でAIによる自動化や高度な連携が必要かを明確にしたうえで、導入を検討することが重要です。
課題を整理して、最適なAI活用を判断する
本記事では、チャットボット運用でよくある課題と改善策、そして従来型チャットボットの限界について解説しました。導入効果が見えにくい、離脱率が高い、運用負荷が大きいといった課題は、改善策を行うことである程度解決できます。しかし、複雑な問い合わせや複数タスクの連携には限界があり、単体のチャットボットだけでは対応が難しい場合もあります。
こうした課題を補うのが、複数のAIが連携して動作するマルチAIエージェント型の仕組みです。連携するAIがタスクを分担し、ユーザーの意図を柔軟に判断することで、単体のチャットボットでは難しい対応も可能になります。
当社が提供する「CAT.AI マルチAIエージェント」は、リードAIエージェントが司令塔となり、複数のAIエージェントが連携して問い合わせ対応や業務自動化を行う仕組みです。テキスト・音声・フォーム・画像などの情報を組み合わせて適切に判断し、ユーザーに最適な対応を提供します。単体のチャットボットでは困難な業務や複雑なシナリオ設計もカバーでき、運用担当者の負荷を軽減しつつ、顧客体験の向上も期待できます。
本記事で解説した内容を整理することで、単体のチャットボットで対応すべきか、マルチAIエージェントの導入を検討すべきかの判断材料が明確になります。さらに、CAT.AI マルチAIエージェントの製品資料を確認することで、導入イメージやシングルAIとの違いを具体的に把握し、自社に最適な次の一手を検討する参考にすることができます。
この記事の筆者

株式会社トゥモロー・ネット
AIプラットフォーム本部
「CAT.AI」は「ヒトとAIの豊かな未来をデザイン」をビジョンに、コンタクトセンターや企業のAI対応を円滑化するAIコミュニケーションプラットフォームを開発、展開しています。プラットフォームにはボイスボットとチャットボットをオールインワンで提供する「CAT.AI CX-Bot」、複数AIエージェントが連携し、業務を自動化する「CAT.AI マルチAIエージェント」など、独自開発のNLP(自然言語処理)技術と先進的なシナリオ、直感的でわかりやすいUIを自由にデザインし、ヒトを介しているような自然なコミュニケーションを実現します。独自のCX理論×高度なAI技術を以て開発されたCAT.AIは、金融、保険、飲食、官公庁を始め、コンタクトサービスや予約サービス、公式アプリ、バーチャルエージェントなど幅広い業種において様々なシーンで活用が可能です。



.jpeg)




